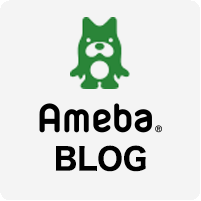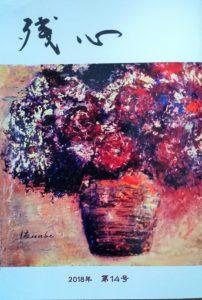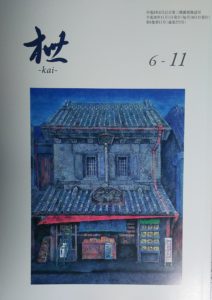「青海波」2018年10月号
「青海波」2018年10月号
主宰 船越淑子 編集 本城佐和
結社誌・月刊・通巻319号・徳島県徳島市・創刊 斎藤梅子
四国で「俳句」といえば、なんといっても俳都・愛媛県松山市が思い浮かぶが、徳島市も負けず劣らず俳句の盛んなところである。
徳島県俳句連盟という団体があり、毎年、連盟主催の俳句大会が開催されている。
県内で10ほどの結社があり、大会は各結社が毎年、持ち回りで運営し、開催するのである。
私も以前、「ひまわり」の西池冬扇主宰に依頼され、そこで講演したことがある。
台風直撃の日であったが、400人近い人が集まっていてびっくりした思い出がある。
今年は「青海波」が担当。
いきなり「編集後記」の話になるが、今年の大会応募句は過去最高の「3540句」も集まった、と淑子主宰が書いている。
応募句の多い少ないは、その年の担当結社の力によるところが大きい。
淑子主宰は、
(「青海波」会員の)青海波への愛を再確認致しました。
と礼を述べている。
このことでも、会員の「青海波」への愛着、「青海波」の底力が伺える。
一つのエピソードを紹介したい。
創刊主宰・斎藤梅子に関することである。
飯田龍太、森澄雄は戦後俳句、特に高度経済成長期の頃の現代俳句の二巨頭である。
その二人が、「現代俳句女流賞」の選考委員をしていた。
女性雑誌「ミセス」を出版する文化出版局が創設した賞で、女性の句集に授与される賞だが、今は消滅している。
だいたい俳句の賞というのは、大御所や大結社主宰が取るものと相場が決まっている。
過去の受賞者も、
桂 信子
鷲谷七菜子
中村苑子
岡本 眸
黒田杏子
と錚々たるメンバーであった。
さて、1985年(昭和60年)の話である。
選考会を数日後に控えていた龍太は、受賞者を決められず悩んでいた。
そこへ森澄雄から電話がかかって来た。
澄雄は興奮気味に、
斎藤梅子という女流俳人を知っているか?
と尋ねた。
龍太は知らないと答えた。
澄雄は、斎藤梅子句集『藍甕』というのがすごくいいから読んでみろ、と言った。
それで龍太も読み、感嘆し、当時、梅子は無名だったが、二人は「現代女流俳句賞」に推薦し、見事に受賞した。
それによって斎藤梅子は一躍、脚光を浴びたわけである。
「青海波」創刊前のことであるから、これは快挙と言っていい。
私は、このエピソードを聞くたび、あらゆる俳句賞が、単なる名誉賞、功労賞になってしまった現代を嘆き、澄雄、龍太という「慧眼」なき現代俳句を悲しむ。
これは「青海波」の人から聞いた話で、「青海波」の人々にとって、このエピソードは「青海波」の誇りなのである。
現在は、梅子氏逝去により、妹の船越淑子さんが継承している。
淑子さんの話を聞くと感嘆する。
梅子氏も淑子さんも、関西で俳句を学ぶため、毎月何度も船に乗り、関西へ出かけたそうである。
当時は明石大橋も鳴戸大橋もなく、関西へ行くのは船しかなかったのだ。
私はその光景、船に乗って鳴門海峡、或いは紀伊水道を渡ってゆくお二人の姿を空想してしまう。
お二人の情熱、志の高さを尊敬するのである。
さて、誌面である。
巻頭の斎藤梅子氏の作品。
十月や魚が目を張る船の胴
火の恋し祖谷は夜へと岳つらね
秋まつり栃の幹より子の出で来
特に1句目は「さすが」と思う。
「目を張る」がいい。
ものすごい臨場感である。
こんな臨場感のある写生句は滅多に見れるものではない。
「船の胴」も実に細かく、巧みだ。
並の才能なら、「船の上」「船の中」程度であろう。
季語「十月」の斡旋も素晴らしい。
青く澄んだ空、海原が見えてくる。
10月号から感銘句を以下に。
戦争が海峡の沖灼けてゐた 船越淑子
まつさらな空の深きへ門火の炎
置き去りの箒真夏の石畳 松村和子
芝居絵の地獄をともす土佐の夏 日野繁子
百畳の開け放たれし蝉の声 竹本良子
初潮や世界遺産へ渦巻けり 濱本紫陽
大橋に晩夏を惜しむ海の色 石井政子
夕焼けて百の島々光り合ふ 本城佐和
燃える燃える空気の燃える炎天下 仁田典子
手のひらで切る水蜜桃の魅惑 長谷川公子
鷺草を咲かせ女は風となり 岩本敏子
夏の夜や山の吐き出す水の音 秋田芳子
あいうえお習つたばかり夏休 佐伯さちこ
関東人の私のとって「青海波」誌を読む楽しさは、阿波や四国の風土ならでは俳句を読めることである。
船越氏の「戦争が」、日野氏の「芝居絵の」、濱本氏の「初潮や」、石井氏の「大橋に」、本城氏の「夕焼けて」がそうである。
こんな俳句は私には逆立ちをしても出来ない。
風土、そして風土俳句というものを眩しく思う。
連載では、
「折々随想」…佐藤 武
「阿波の藍甕」…堤 高数
などがある。
手前味噌だが8月号より、
「管見」…林 誠司
つまり私が執筆を担当している。
これは、「青海波」会員作品鑑賞である。