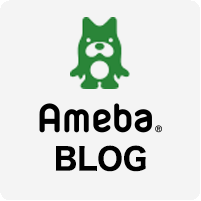行動力の人 落合美佐子句集『野菊晴』鑑賞 「絵空」 中田尚子
『野菊晴』は、落合美佐子さんの第三句集である。平成七年から三十年までの約四百句が収められる。母として娘として、また「浮野」落合水尾主宰の妻として、同誌編集委員として、いくつもの立場をこなしてこられた軌跡がここにある。
母ふたり健やかに老い野菊晴
句集名となった一句。平成十三年作。「母ふたり」は当然夫の母と実母である。健やかに老いることのめでたさ、「野菊晴」にそれが象徴される。そして、作者自身がそのことを実感する年齢に差しかかっていたと思う。さらに母の句を挙げる。
悼 五月二十九日 義母九十歳
天寿いま涼しき音の骨拾ふ
涼しさの日々を重ねて白寿かな
百歳を立たせて青き踏ましむる
櫨紅葉百一歳の童女めく
母を置く老人施設花菜畑
一人静遠くへ母を置きしまま
「健やかに老い」し母の変化に、本句集二十三年間の時の重さを感じる。「涼しき骨」に籠もる義母への尊敬と感謝。「白寿」「百歳」「百一歳」には敬服するばかりだが、「立たせて青き踏ましむる」の娘の祈りと行動が胸を打つ。その母を「老人施設」に「置きしまま」にしなければならないことへの罪悪感と哀しみ。読み手は我が身に重ねて深く共感する。あとがきに、母上が百二歳の今も元気でおられることが記されていて、ああよかったと思う。母上の豊かで幸せな人生は、美佐子さんの存在なしにはあり得なかった。これからも、母上は、美佐子さんのほとりで安らかな時を過ごされるだろう。
『野菊晴』には、この他にも家族の句が多く、家族史として読める一面をもっている。
うちの娘でゐられる日数秋ざくら
日向ぼこ胎児ぽこぽこ動き出す
新生児うららか足に名を書かれ
さあ行かう帽子手袋三輪車
かあさんとばあちやん似てるねといとど
母としての眼差しに、初孫を得て祖母としてのそれが加わった。第一句には自解がある。〈名字が変わる。吾が家の娘でなくなる。他人様の名字が付く。あと何ヶ月、あと何日、うちの子でいられるのか。〉(「浮野」30年11月号)このブルーな思いも、初孫が吹き飛ばす。「胎児ぽこぽこ」の弾みに押さえきれない喜びと期待が表出。「新生児」は初孫秀之さんの名が前書きに。そして、この後生まれる二人のお孫さんにも、祖母は句を贈っている。「さあ行かう」は楽しさが溢れる。「三輪車」で情景が一気に浮かぶ仕掛けが見事だ。この作者の句には口語調が時々表れる。「かあさんと」もそうだが、日常会話のさりげないことばが、こんなにも一句に馴染んでしまうとは。後者は孫のことばであろうが、そんなことを言うようになったと目を細めている作者が見えてくる。
去年今年医師の言葉を力とす
二十六年作。最終章「白梅」の冒頭に置かれた句。「十二月二十七日水尾脳梗塞にて入院」と前書きが付く。〈「浮野」の行方はどうなるのかと、闇黒の谷へ落ちていくような思い〉であったとあとがきに記されている。がっしりと見るからに健康体の水尾先生であれば、青天の霹靂ともいう出来事であったろう。ご家族はじめ結社の人々の動揺は大きかったに違いない。
たてがみの欲しき今なり初山河
しかし、主宰の妻として今こそ己を奮い立たせ、立ち向かおうとする決意をもつのである。水尾先生の句集『円心』(二十七年刊)のあとがきに次の一節が見える。〈妻の美佐子には格別世話になった。介護・家事・渉外・編集等、言葉にならないほどである。〉
少しづつ癒えて応へて五日かな
七日過ぐ遠山脈に守られて
山笑ふ癒えて我儘ふえてきて
さらには
青田中予後とも見えぬ歩きぶり
パナマ帽先生ぐんと若くなる
「たてがみの」の後に続く句群にほっとさせられる。水尾先生は順調に快復され、以前にも増してお元気になられたのである。
さて、「浮野」今号(30年12月号)に和泉好遺句集『在るがまま』特集が組まれている。和泉好さんは水尾先生の実弟で下田在住の俳人であった。三回忌に当たって上木された句集である。『野菊晴』最終章には、悼句が置かれている。
納棺や山抱き入るる夕時雨
冬北斗召されて海を輝かす
野水仙海へ喪心ただよはす
「浮野」の特集と合わせて読み、遺句集を改めて読んだ。よき兄弟、よきご家族である。
もう一人、触れておきたい人と美佐子さんの関わりがある。「浮野」の編集長を長く務められた河野邦子さんである。
利休忌や下肢切断の覚悟とは
河野さんは、「浮野」を支え牽引する、美佐子さんにとっては頼れる同志ともいうべき存在ではなかったかと想像する。その人から右足切断の覚悟を告げられたのである。
逝く人の側にそのまま春の服
冴返る遺品めきたる庭の木木
来てるはず花人として見てるはず
三年後河野さんはついに亡くなられる。明るい色の「春の服」が悲しみを深くする。「庭の木木」を見ても思い出が蘇り、何度も共にした桜には「花人として」訪れている魂を感じずにはいられない。私事になるが、筆者も河野さんには長年お世話になった。元小学校の教師をしていた河野さんは、俳人協会で教師向け講座の担当をされていて、私は講座委員の一人である。講座を知り尽くし、隅々に隈無く配慮されていた河野さんはなくてはならない方だった。ひょうひょうとしていて、声高ではないけれど言うべき事をおっしゃる方だった。だから、作者の気持ちが私にも少しはわかる。水尾先生と共に、美佐子さんは今も毎月、河野さんの仏前に「浮野」を持参されるのだという。
こうして見てくると、四章「羊蹄花」から最終章「白梅」にかけての数年間は、作者にとってつらいことの多い日月だったことがわかる。しかし、そんな作者を励ますのもやはり俳句なのである。
春ショール八十路の坂を踏み出せり
は力強く頼もしい。「春ショール」の軽やかさがよい。乗り越えて歩き始めた作者の矜恃がうかがえる。
ここからは、心に残ったその他の句に触れていこう。
美佐子さんの俳句の始まりは「水明」である。
つなぎたる手の熱いまもかな女の忌
かな女忌や丸の上手に書けたる子
秋子忌の赤きマフラー手離さず
秋子忌の椿を挿して心とす
「つなぎたる」は『野菊晴』掉尾を飾る。自解(前出)に席題でできたと記されているが、『山月集ー忘れえぬ珠玉ーかな女の句 秋子の句』(落合水尾)に、こんな一節がある。
東京銀座のおしるこ屋若松の句会にはかな女の杖となってよく出かけた。
かな女の掌はやわらかくて大きかった。
水尾先生若き日のエピソードがベースになっている。「丸の上手に書けたる子」は、「浮野」の作家ならではの作と思う。かな女の教えに〈俳句は、マルを描いて、それに立体感をつけて、自身はその影にそっと居るように表現すればよい〉があるからだ。幼子の描いた丸は絵の一部であったろうが、師の教えがまざまざと蘇った瞬間だ。「赤きマフラー」を手放さなかったのは作者ではなく夫に違いない、と思っていたら「買初めや赤と決めたる夫のもの」を見つけて思わずにやりとした。「椿を挿して心とす」は椿が季語以上の力を発揮している。秋子忌の作には、秋子らしい華やぎが備わり、在りし日の姿を偲ばせる。
蚊をつれて動物園を出でにけり
滑り台落花の中にとび出せり
初山河炎のいろの琴袋
膝掛けやすぐ眠くなる年を取る
浮かぶたび遠のいてゆく鳰
「蚊をつれて」のユーモア、「落花の中に」のスピード感、「炎のいろ」の激しさ、「年を取る」の自然体の潔さ、「遠のいてゆく」の確かな措辞。どれもみな小気味よい読後感に満たされて、特に好きな句だ。
美佐子さんは多くの旅をされてきた。
秋の夜や神を呼び出す笛太鼓(国東・高千穂)
納沙布の海霧に眉濃き夕べかな
城塞を海に傾け冬夕焼(イタリア)
潮騒かはた神集ふ水音か (出雲神社祭)
爽やかに靴音はづむシャンゼリゼ
フットワーク軽く、どこへでも出かけられるが、この行動力が美佐子さんの人生を作り上げてきたのだと思う。度々の引用になるが、「浮野」12月号の編集後記で〈一か月ほど前も、東京例会の後、突然日立海浜公園のコキアを見たいと宿も取らずにご夫妻で出かけていきました。相当歩かれたようです。〉と、龍野龍さんを心配させている。しかし、お二人は、これからもきっと、少し回りをはらはらさせながら自由自在に羽ばたかれることだろう。美佐子さんの作品に今後それがどう結実していくか、楽しみに拝見していたい。
利酒の良き名浮足立ちにけり
ほとんどお目にかかったことのない美佐子さんと、いつの日か酌み交わしたいものだ、とそんなことを考えてしまった。