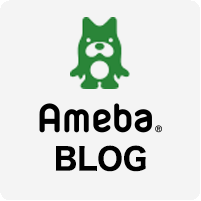句集『るん』を読む 行方克巳~「知音」共同代表
句集『るん』を荒読みし、またじっくりと読み返してみて、多少の戸惑いを感じながら、この文章を書き始めた。
しかし、私流の視点で読んでゆくほかはあるまい。
豆腐屋の声遠ざかる四温かな
谷底に町閉ぢ込めて鳥曇
春昼や徒歩十分に母のゐて
紙風船破いたやうにポピー咲く
母留守の家に麦茶を作り置く
目瞑りて話す男の夜長かな
読み初めは野菜とろとろ煮る時間
これらの句は、私が日頃馴染んでいる仲間達と全く同じスタイルといってよい。
私の麻乃さんのイメージとは大分異なる。
<わが師系風生敏郎草の花>という拙句があるが、私の句も句の読み方も師系とそれほど外れてはいない。
そしてここにあげた麻乃さんの句は、まさに私達の詠み方なのである。
「豆腐屋」の句は、四温という季がよく働いている。
「谷底」の句は、「閉ぢ込めて」が作者らしいところだろう。
「麦茶」の句には、母自身は登場しないが歩いて10分ほどの所に住んでいる母親との日常的関わりがよく見えてくる。
「目瞑りて」の句はある種の男が彷彿する。
「とろとろ」というオノマトペの用い方はまことに当を得ている。
就中「紙風船」の句に私は心を引かれた。ポピーの咲きざまを、まるで紙風船を破いたようだと形容したその視線には単にそのものの形状を写し取ろうという以前に、作者の詩的直感が働いている。この比喩には作者の個性が垣間見えていよう。
電柱の多きこの町蝶生まる
屋根に屋根重なる街や鰯雲
麻乃さんの住む町の一端が過不足なく紹介されている。
しかし、どうやら麻乃さんの俳句の向うところは少し異なる方向にあるようだ。
カピタンの女郎部屋にも春埃
雛の目の片方だけが抉れゐて
砂利石に骨も混じれる春麗
夜学校「誰だ!」と壁に大きな字
カピタンの句を私は正確にパラフレーズすることはできないが、「カピタン」「女郎部屋」「春埃」と並べると何か不思議な空間が顕ち現われてくるような気がする。
片目が抉られている雛のイメージはまことにおぞましい。
事実ありのままというより、作者の心象風景の中で形成されたイリュージョンと言っていいと思う。
そういう素地が作者の心奥に存在するということだ。
麻乃さんは私の知る限り、いつでもまことに屈託がなさそうに見える。
この句はその麻乃さんの心奥を覗き込むような恐ろしさがある。
砂利に混在する骨も同様、「春麗」という明るい季で収めているだけ、より不気味である。
「誰だ!」とは一体何を意味するのかは全く分からない。
しかし、壁に大書された「誰だ!」もまた、作者の心の叫びなのかも知れない。
句集の帯に、
詩人・岡田隆彦を父に、
俳人・岡田史乃を母に、
詩歌の世界から
生まれてきた作者…
とある。
岡田隆彦氏は慶大卒の詩人で、かつて三田文学の編集長であった。
私は未見であるが、彼には『史乃命』という詩集があるという。
その史乃さんについて、いくつもの句が『るん』に鏤められている。
母留守の納戸に雛の眠りをり
振り向きて母の面影春日傘
母からの小言嬉しや松の芯
母入院「メロン」と書きしメモ一つ
母見舞ふ秋空へ漕ぐペダルかな
帰りたいと繰り返す母冬夕焼
お母さんは自分の思いをストレートに伝える人のようだ。
健康を損ねて入院した時も自分の意思をそのまま作者に伝えようとする。
「メロン」とだけ書いた走り書きは、大好きなメロンを持って来るようにとの厳命だろう。
早く退院して家に帰りたいという気持ちを、まるで子供のように露わにするのもいかにも史乃さんらしい。
父親の隆彦氏に対する作者の思いはかなり複雑なようだ。
凡人でありし日の父葱坊主
夏シャツや背中に父の憑いてくる
神無月父だけのゐる神道山
おお麻乃と言ふ父探す冬の駅
早くに世を去った父隆彦氏は麻乃さんにとってきわめて大切な存在であり、それは今でも変わることはない。
普段の父は、よその誰の父親とも変わることのない、只のやさしい父である。
しかし、彼女が何らかの思いにとらわれて身動きできないような時、ともすれば後退を余儀なくされそうな時、そんな時自分の思いを前へ前へと推し進めてくれるような不思議な父の手を感じる。
自分を強く支えてくれるような父の手を背中にはっきりと感じるのである。
麻乃さんには、大人になり切ることを拒むかのようなそんな意識があるのでは、と思うことがある。
いつまでも父の子供でいたいという願望―――。
それが彼女の屈託のなさ、天真爛漫な人となりにつながっているように思う。
「やあ麻乃! こっちにおいで」という父の声を今でも追い求めているのだ。
最初に私の感じた戸惑いはこのような麻乃さんの魂の経歴が作用していたのかも知れない。
『るん』には私の師系の句を読むようにすんなりと腑に落ちる部分と、そうでない部分が明らかに混在している。
これは俳と詩の混在ともいえるかも知れない。
まさに<身ぬちにも父母のまします衣被>の、父母の混在である。
これまで私が取り上げてきた句は、俳句表現と詩的モチーフがよいマッチングを見せていた句である。
俳句は十七音の言語表現であるから、ある意味での正確性も必要とされる。
例えば、
昨日から今日になる時髪洗ふ
という句、理屈っぽいようだが、昨日から今日になるのではなくて、今日が明日になり、明日になってはじめて昨日が存在し得るのである。
松の木小唄の「雪に変わりがないじゃなし」と同じように受容してもよさそうではあるが、私にはやはり気になることの一つである。
春疾風家ごと軋む音のして
については、「春疾風」「軋む」とあれば下五の「音のして」は蛇足となる。
下五に別の工夫が必要だろう。
最後に私が最も興味を持った一句を上げて了りたい。
思春期や怒つた顔で薔薇を買ふ
作者には、
小袋に蜜柑を入れて子は家出
の句があるが、この只今思春期まっ只中の少女(?)は麻乃さんのお嬢さんか。
一句に、かつての自己を投影させているのは確かであるが、複雑な青春時代の微妙な心のありようを活写した句として深く印象に残った。
こうして気ままに『るん』を読んでみて感じるのは、この作者はきっと何かを匿し持っている、という予感である。
それがどのように発展するか分らぬが、そういう印象を強く持ったということを書き添えて置きたい。