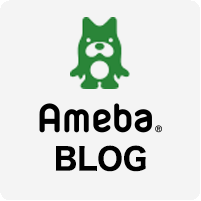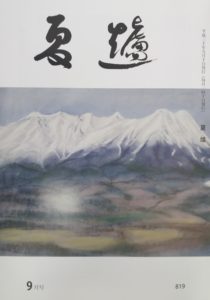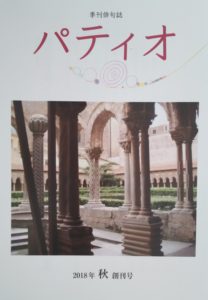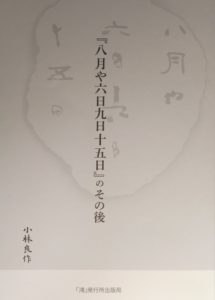日下野由季句集『馥郁』
著者:日下野由季(ひがの・ゆき)
句集名:馥郁(ふくいく)
第二句集 ふらんす堂 平成30年9月25日刊行
ひとりではなくて北窓ひらきけり
日下野由季さんの待望の第二句集。
30代より「海」編集長を務める俊英である。
私が編集長時代、文學の森主催の山本健吉評論賞を受賞している。
記憶があいまいだが、おそらく女性初の受賞者である。
師である高橋悦男「海」主宰の師、野澤節子の評論で、選考委員の大輪靖宏・坂口昌弘両氏とも1位で一致し受賞した。
このように書くと、「理論派の人」と思われるかもしれないが、そうではない。
むしろ俳句に於いては「しなやかな感性の人」というイメージがある。
30歳で刊行した第一句集「祈りの天」もしなやかな感性に満ちた好句集だったが、今回はそれに「豊かな静けさ」が加わった感がある。
「祈りの天」にそういう部分がなかったわけではないが、どこか、青春や若さゆえのざわざわとした心の揺れがあった。
もちろんそれも若き俳人の作品特有の魅力で、それが悪いという意味ではない。
ただ、今回の「馥郁」は、句集名を較べてみるとわかるように、どこか心の安定が伺え、それが俳句の「純度」を高めている。
感銘句を以下に。
揺れやむは泣きやむに似て藤の花
桐咲くや忘れしころに来る手紙
径ゆづるとき秋草に濡れにけり
風を聴くかたちとなりてうす氷
まだ見つめられたくて鴨残りけり
虹を見しことをはるかな人に告ぐ
羅を水のごとくに纏ひけり
またひとつ星の見えくる湯ざめかな
ただ晴れて虚子忌の空のありにけり
吹かれたるままに歩きて花の岸
春の山生きるものとは光るもの
まほろばの風はるかより更衣
ポンプ井戸押せば夏日の迸る
今日の月思ふところに上がりけり
秋めくとショパンに針を下ろしけり
詩に生きて人悲します啄木忌
口づけを受く手の甲や夜半の秋
朝霧や眠らぬ街をゆく運河
水澄めり受胎告知のしづけさに
鳥雲に入る灯台に窓一つ
さかしまに叩く屑籠花ぐもり
てのひらに指で書く字や蝶生まる
流星の強く短く山の端
大空を来て水鳥となりにけり
いきいきと巌の生まるる春の潮
紫陽花の大きく白を尽くしけり
鳶の輪のゆるむことなき初御空
星涼しいのち宿るをまだ告げず
こうし見ると、やはり、『祈りの天』の頃の「ざわざわ」としたものが消えている。
彼女の俳句は「心から湧いてくるもの」を基調としている。
そして、その心は常に汚れてはならないもの、でなければならない。
栞文は大木あまりさんが執筆。
あまりさんは、彼女の俳句について、
感性の豊かさ、柔軟な発想が際立っている
と述べ、
どのページをめくっても、透明な句に出会うことができる
と称賛している。
掲句は私がもっとも感銘した句。
「ひとりではない」とはご主人のことか、或いは、この句のあとに出てくる、身の内に宿った命のことか。
「ひとりではない」ということは、以前は「ひとり」だった、ということである。
もちろん家族にも、句友にも恵まれている彼女だが、若さゆえの「孤独感」というものはあっただろう。
人はおのれの使命や生きがいを見いだした時、孤独を忘れることができる。
私にはこの句は、妻として母として、そして自分の俳句人生を含めた人生というものに確固たる「道」を見つけたことへの喜びの一句であると思う。
「北窓」は「迷い」を象徴している、と考えていい。