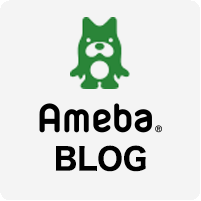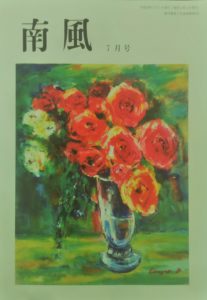師岡洋子句集『水の伝言』
一片の花びらのごと鵙の贄 洋子
(ひとひらの はなびらのごと もずのにえ)
師岡洋子(もろおか・ようこ)「鳰の子」同人の第一句集。
文學の森刊。
驚いた。
この方は本当にうまい。
俳句の世界で「うまい」という言葉は、あまり、褒め言葉として使われていないが、これはいい意味で言っている。
おおまかな表現だが、句に「雑味」がない。
多くの人が、一句に過剰な「詩」や「情」を加えよう、或いは技術的に優れたものにしようと「余計な表現や言葉」を加える。
また、同じように、雑味のある「二句一章」にしようとする。
私が言っている「雑味」というのは、過度な言葉の装飾、情の押しつけ、無理のある二句一章などである。
『水の伝言』にはそういうものがない。
まるで高野素十の「純粋写生」を読んでいるようである。
それでいて、句が面白く、溌剌としている。
天賦の才を感じる。
プール出る鬣のごと水を引き
小窓ある箱で届きしカーネーション
青芝に乾杯の卓ととのへり
新藁の匂ひまみれの仔犬かな
もう少し降ればよい雨ねこじやらし
縫初はまづとれさうな釦つけ
帯解きてよりの喪心春深し
雪折や名所をつなぐ竹の道
蟋蟀の隠るる雨の大工箱
にじみたるやうに川暮れ祭笛
どの句にも破たんがない。
そういう句集はある意味、淡白で物足りなさを感じてしまうものだが、『水の伝言』にはそういうものがない。
写生の眼がしっかりしていることもあるだろう。
さらに、二つほどのことを指摘したい。
柴田多鶴子「鳰の子」主宰の序文や著者略歴にあるように、作者は元「ぐろっけ」(品川鈴子主宰)の所属であった。
品川鈴子さんの「ぐろっけ」は山口誓子門である。
柴田主宰も、誓子門の系統と考えていい。
誓子俳句の素晴らしさはいろいろあるが、私は「もの」の存在感が巨大であることを挙げたい。
今風に言えば、「もの」の存在感が「半端ない」ことである。
七月の青嶺まぢかく熔鑛爐
の「熔鑛爐」、
夏の河赤き鉄鎖のはし浸る
の「鉄鎖」、
蟋蟀が深き地中を覗き込む
の「蟋蟀」、
海に出て木枯帰るところなし
の「木枯」、
扇風機大き翼をやすめたり
の「翼」、
夏草に汽罐車の車輪来て止る
の「車輪」などなど。
もちろん「もの」で詠う伝統は、高浜虚子の「ホトトギス」の伝統でもあるが、この存在感の強さは「ホトトギス」以上である。
無機質な塊が一句の中にデンと存在している。
『水の伝言』にもそれがある。
上記の句で言えば、
プール出る鬣のごと水を引き
の「鬣」、
雪折や名所をつなぐ竹の道
の「竹の道」、
蟋蟀の隠るる雨の大工箱
の「大工箱」、
にじみたるやうに川暮れ祭笛
の「祭笛」(これは「もの」というより「音)、
或いは、
吊橋を大きく揺らす登山靴 洋子
の「登山靴」。
「吊橋を揺らす」などという表現は腐るほどあるが、この「登山靴」の存在感はどうだろう。
登山を済ませて来たのか、意気揚々と吊り橋を渡ってくる登山者の様子を「登山靴」という「もの」で表現している。
ここに誓子に連なる「ぐろっけ」「鳰の子」の系譜を見る。
現代はしゃべり過ぎ俳句、感覚・情緒優先の俳句が氾濫している。
その中で、俳句の本来の素晴らしさ、未来への可能性を示唆してくれる句集である。
もう一つ言いたい。
これは、上記の「もの」と関連している。
『水の伝言』を読んでいる最中、私は、高浜虚子のある文章を思い出した。
引用する。
俳句を十七字を以て詩の体となす。
すでに十七字を以て詩の体をなす以上は、散文のごとく、上下に引き続く語勢を有すべからずして、その中には中心点あり、首尾あらざるべからず。
切字はすなはち十七字をして首尾あらしめ中心点あらしむる所以にして他の語を以ていへば、句にしまりあらしむるなり。 高浜虚子『俳句入門』
虚子は「切れ字論」などというものはさして大切なものではない、と言い、上記のことを書いている。
つまり、いい句には「中心点」というものがあり、それがあれば自然と「切れ」は生まれているのだ、と述べている。
詳しいことは以前、ブログに書いたことがあるので、そちらを読んでいただきたい。
ブログ「虚子は切れ字は大切ではない」と言った?
https://blogs.yahoo.co.jp/seijihaiku/17043973.html
さきほどの「もの」は、まさしく句の「中心点」となっている。
それゆえ、自然と切れも生まれていて、読んでいて鮮明な印象を覚えるのである。
いい俳句をつくろうと思い、それが達成できれば、自然と技術や技法は、句の中に納まっている、ということだ。
さて、冒頭の句である。
この句も同様の効果があり、句集の中でもっとも印象深かった。
「もの」の存在感、一句の中心点がまったくぶれていない。
誰だったか忘れたが、芸術というのは、ものに生命を吹き込むことだと言う。
この「鵙の贄」は、この句によって「永遠のいのち」が吹きこまれ、「一片の詩」となったのだ。
詩歌の力の本質を見たような気がする。