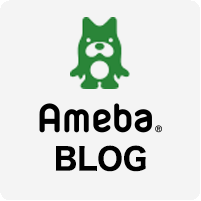高波にかくるる秋の燕かな 飯田蛇笏(いいだ・だこつ)
(たかなみに かくるる あきの つばめかな)
燕は晩春、日本にやってきて、秋に南へ帰ってゆく。
地方によっては時期が違うかもしれないが、私の住むあたりでは田植の頃、ゴールデンウイークの前にちらほらと姿を見かけるようになり、田植の頃には、水を張った田、苗を植えたばかりの田を鮮やかに飛び回っている。
「秋に帰る」と書いたが、いったいいつ頃に帰るのだろう。
私のイメージとしては10月くらいだと思っていたが、最近(8月下旬)、空を見上げてもあまり燕を見かけなくなった。
5月、6月あたりは、子燕なども交じって、たくさん飛んでいたのだが…。
歳時記を見ると、
9月頃になると…
と書いてあった。
もう、そろそろと帰り始めているのだろうか。
掲句。
飯田蛇笏(明治18年(1885)~昭和37年(1962))は「雲母」(うんも)主宰。
四男は俳人で、二代目「雲母」主宰、昭和を代表する俳人・飯田龍太である。
早稲田大学時代に早稲田吟社に所属し、一時期、松根東洋城にも師事したが、のちに「ホトトギス」に入会し、高浜虚子に師事した。
山梨県東八代郡五成村(のち境川村、現在は笛吹市)の大地主の長男として生まれる。
早稲田大学を中退。
同級生に若山牧水がいる。
芥川龍之介は、蛇笏の句を高く評価し、蛇笏の影響を受けた句も残している。
強烈な主観で風土に根差した自然詠を多く残した。
句の声調の正しさ、格調の高さから「タテ句最後の人」とも称され、大正時代全盛期を迎えた「ホトトギス」の四天王の一人として活躍した。
ちなみに四天王の残りの三人は、原石鼎、村上鬼城、前田普羅。
それぞれの代表作を列記してみる。
芋の露連山影を正しうす 飯田蛇笏
冬蜂の死にどころなく歩きけり 村上鬼城
頂上や殊に野菊の吹かれをり 原 石鼎
雪解川名山けづる響かな 前田普羅
思い切り簡単に説明すると、
蛇笏は「タテ句」の人
鬼城は「境涯詠」の人
石鼎は「風土詠」の人
前田普羅は「自然詠」の人
である。
「風土詠」と「自然詠」は同じじゃないか、と言われそうである。
わたしの中では微妙に違う。
石鼎の風土詠には「人生」が乗っている。
風土に生きる自分が投影されているのだ。
普羅は純粋な自然詠である。
もっとも普羅は、その後大きく句柄が変容するのだが、今回は蛇笏の話をしたいので、ここでは触れない。
さて、蛇笏だが、さきほど芥川龍之介も影響を受けた、と書いた。
龍之介の一文を紹介しよう。
「或時(あるとき)歳時記の中に「死病得て爪美しき火桶かな」と云う蛇笏の句を発見した。
この句は蛇笏に対する評価を一変する力を具えていた。
僕は「ホトトギス」の雑詠に出る蛇笏の名前に注意し出した。
勿論その句境も剽窃した。
「癆咳の頬美しや冬帽子」
「惣嫁指の白きも葱に似たりけり」
――僕は蛇笏の影響のもとにそう云う句なども製造した。」
芥川龍之介『飯田蛇笏』
蛇笏の句に感銘し、自分の句のモチーフや表現の参考にしていたころがわかる。
蛇笏が実家を継ぐため、早稲田大学を中退し、山梨に戻った折、その文才を惜しんだ若山牧水が押しかけ、説得した、というエピソードもある。
牧水も、龍之介も蛇笏を高く評価していたことがこのことからもわかる。
さて、もう一つ、「タテ句」について述べたい。
俳句界最高峰の賞の一つに「蛇笏賞」がある。
文字通り、飯田蛇笏の名を冠した賞である。
俳句界最高の賞がなぜ「子規賞」でもなく。「虚子賞」でもないのか、と疑問に思う人もいるだろう。
簡単に言えば、賞の創立者である角川源義が、蛇笏の俳句に惚れ込んでいたからである。
(こまかいことはこちらを…)
蛇笏賞について
「タテ句」とは、だいたいこういうことである。
① 連句の座で一番最初に詠む句。発句。
② 厳然と屹立している句。気高く力強い立ち姿を持っている句。
③ 一句が完全に独立している句。
蛇笏を「タテ句の人」と呼ぶ、この「タテ句」はこの場合、②③になる。
「現代の俳人の中で堂々たるタテ句を作る作者は蛇笏をもって最とすると誰かが書いていたのを読んだことがあるが、そのことはまず氏の句の格調の高さ、格調の正しさについて言えることである。(略)俳句の持つ格調の高さ、正しさにおいてついに彼の右に出づる者は見当たらぬのである。」
「その気魄に満ちた格調の荘重さ、個性の異常な濃厚さは、蛇笏調をして俳諧史上に独歩している。」
山本健吉『現代俳句』
「蛇笏を芭蕉以上に、近代俳句の得がたき作家とする理由は、芭蕉はいちめん連句の人で、付句(つけく)の名人であり、恋の句の達人であった。
言ってみれば、物語的な世界がいつまでも尾鰭のようについていた。
蛇笏は全くそれを捨てて立句(発句)一本に生きた唯一の俳人である。」 角川源義「近代俳句と飯田蛇笏」
であるから、本来、「蛇笏賞」は「タテ句の人」に贈る賞であるべきなのだが、今はそういうこととは関係なく贈られているようだ。
以上を踏まえて、あらためて、掲句を見てみれば、蛇笏の「タテ句」の魅力がわかってもらえると思う。
一句に気魄が満ち、「調べ」に格調がある。
秋の高波が崩れる前にすり抜けてゆく燕の姿、そして、「ドドーン」と崩れてゆく高波の音が、腸に響いてくるようではないか。
『飯田蛇笏のその他の作品』
たましひのたとへば秋のほたるかな
一鷹を生む山風や蕨伸ぶ
極寒のちりもとどめず巌ふすま
をりとりてはらりとおもきすすきかな
くろがねの秋の風鈴鳴りにけり
わらんべの溺るるばかり初湯かな
日も月も大雪渓の真夏空
つりそめて水草の香の蚊帳かな
しばらくはあられふりやむ楢林
ふりやみて巌になじむたまあられ
日輪にきえいりてなくひばりかな
炎天を槍のごとくに涼気すぐ
鈴の音のかすかにひびく日傘かな
戦死報秋の日くれてきたりけり
むらさきのこゑを山辺に夏燕
流灯や一つにはかにさかのぼる
川波の手がひらひらと寒明くる
古き世の火の色うごく野焼かな
夏来れば夏をちからにホ句の鬼
一生を賭けし俳諧春の燭
誰彼もあらず一天自尊の秋