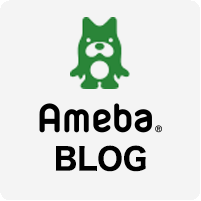渡邉美保句集『櫛買ひに』が大井恒行ブログ「日々彼是」で紹介されました!
アーカイブ
渡邉美保句集『櫛買ひに』が栗林浩氏のブログで紹介されました!
中田尚子「絵空」同人~落合美佐子句集『野菊晴』を読む
行動力の人 落合美佐子句集『野菊晴』鑑賞 「絵空」 中田尚子
『野菊晴』は、落合美佐子さんの第三句集である。平成七年から三十年までの約四百句が収められる。母として娘として、また「浮野」落合水尾主宰の妻として、同誌編集委員として、いくつもの立場をこなしてこられた軌跡がここにある。
母ふたり健やかに老い野菊晴
句集名となった一句。平成十三年作。「母ふたり」は当然夫の母と実母である。健やかに老いることのめでたさ、「野菊晴」にそれが象徴される。そして、作者自身がそのことを実感する年齢に差しかかっていたと思う。さらに母の句を挙げる。
悼 五月二十九日 義母九十歳
天寿いま涼しき音の骨拾ふ
涼しさの日々を重ねて白寿かな
百歳を立たせて青き踏ましむる
櫨紅葉百一歳の童女めく
母を置く老人施設花菜畑
一人静遠くへ母を置きしまま
「健やかに老い」し母の変化に、本句集二十三年間の時の重さを感じる。「涼しき骨」に籠もる義母への尊敬と感謝。「白寿」「百歳」「百一歳」には敬服するばかりだが、「立たせて青き踏ましむる」の娘の祈りと行動が胸を打つ。その母を「老人施設」に「置きしまま」にしなければならないことへの罪悪感と哀しみ。読み手は我が身に重ねて深く共感する。あとがきに、母上が百二歳の今も元気でおられることが記されていて、ああよかったと思う。母上の豊かで幸せな人生は、美佐子さんの存在なしにはあり得なかった。これからも、母上は、美佐子さんのほとりで安らかな時を過ごされるだろう。
『野菊晴』には、この他にも家族の句が多く、家族史として読める一面をもっている。
うちの娘でゐられる日数秋ざくら
日向ぼこ胎児ぽこぽこ動き出す
新生児うららか足に名を書かれ
さあ行かう帽子手袋三輪車
かあさんとばあちやん似てるねといとど
母としての眼差しに、初孫を得て祖母としてのそれが加わった。第一句には自解がある。〈名字が変わる。吾が家の娘でなくなる。他人様の名字が付く。あと何ヶ月、あと何日、うちの子でいられるのか。〉(「浮野」30年11月号)このブルーな思いも、初孫が吹き飛ばす。「胎児ぽこぽこ」の弾みに押さえきれない喜びと期待が表出。「新生児」は初孫秀之さんの名が前書きに。そして、この後生まれる二人のお孫さんにも、祖母は句を贈っている。「さあ行かう」は楽しさが溢れる。「三輪車」で情景が一気に浮かぶ仕掛けが見事だ。この作者の句には口語調が時々表れる。「かあさんと」もそうだが、日常会話のさりげないことばが、こんなにも一句に馴染んでしまうとは。後者は孫のことばであろうが、そんなことを言うようになったと目を細めている作者が見えてくる。
去年今年医師の言葉を力とす
二十六年作。最終章「白梅」の冒頭に置かれた句。「十二月二十七日水尾脳梗塞にて入院」と前書きが付く。〈「浮野」の行方はどうなるのかと、闇黒の谷へ落ちていくような思い〉であったとあとがきに記されている。がっしりと見るからに健康体の水尾先生であれば、青天の霹靂ともいう出来事であったろう。ご家族はじめ結社の人々の動揺は大きかったに違いない。
たてがみの欲しき今なり初山河
しかし、主宰の妻として今こそ己を奮い立たせ、立ち向かおうとする決意をもつのである。水尾先生の句集『円心』(二十七年刊)のあとがきに次の一節が見える。〈妻の美佐子には格別世話になった。介護・家事・渉外・編集等、言葉にならないほどである。〉
少しづつ癒えて応へて五日かな
七日過ぐ遠山脈に守られて
山笑ふ癒えて我儘ふえてきて
さらには
青田中予後とも見えぬ歩きぶり
パナマ帽先生ぐんと若くなる
「たてがみの」の後に続く句群にほっとさせられる。水尾先生は順調に快復され、以前にも増してお元気になられたのである。
さて、「浮野」今号(30年12月号)に和泉好遺句集『在るがまま』特集が組まれている。和泉好さんは水尾先生の実弟で下田在住の俳人であった。三回忌に当たって上木された句集である。『野菊晴』最終章には、悼句が置かれている。
納棺や山抱き入るる夕時雨
冬北斗召されて海を輝かす
野水仙海へ喪心ただよはす
「浮野」の特集と合わせて読み、遺句集を改めて読んだ。よき兄弟、よきご家族である。
もう一人、触れておきたい人と美佐子さんの関わりがある。「浮野」の編集長を長く務められた河野邦子さんである。
利休忌や下肢切断の覚悟とは
河野さんは、「浮野」を支え牽引する、美佐子さんにとっては頼れる同志ともいうべき存在ではなかったかと想像する。その人から右足切断の覚悟を告げられたのである。
逝く人の側にそのまま春の服
冴返る遺品めきたる庭の木木
来てるはず花人として見てるはず
三年後河野さんはついに亡くなられる。明るい色の「春の服」が悲しみを深くする。「庭の木木」を見ても思い出が蘇り、何度も共にした桜には「花人として」訪れている魂を感じずにはいられない。私事になるが、筆者も河野さんには長年お世話になった。元小学校の教師をしていた河野さんは、俳人協会で教師向け講座の担当をされていて、私は講座委員の一人である。講座を知り尽くし、隅々に隈無く配慮されていた河野さんはなくてはならない方だった。ひょうひょうとしていて、声高ではないけれど言うべき事をおっしゃる方だった。だから、作者の気持ちが私にも少しはわかる。水尾先生と共に、美佐子さんは今も毎月、河野さんの仏前に「浮野」を持参されるのだという。
こうして見てくると、四章「羊蹄花」から最終章「白梅」にかけての数年間は、作者にとってつらいことの多い日月だったことがわかる。しかし、そんな作者を励ますのもやはり俳句なのである。
春ショール八十路の坂を踏み出せり
は力強く頼もしい。「春ショール」の軽やかさがよい。乗り越えて歩き始めた作者の矜恃がうかがえる。
ここからは、心に残ったその他の句に触れていこう。
美佐子さんの俳句の始まりは「水明」である。
つなぎたる手の熱いまもかな女の忌
かな女忌や丸の上手に書けたる子
秋子忌の赤きマフラー手離さず
秋子忌の椿を挿して心とす
「つなぎたる」は『野菊晴』掉尾を飾る。自解(前出)に席題でできたと記されているが、『山月集ー忘れえぬ珠玉ーかな女の句 秋子の句』(落合水尾)に、こんな一節がある。
東京銀座のおしるこ屋若松の句会にはかな女の杖となってよく出かけた。
かな女の掌はやわらかくて大きかった。
水尾先生若き日のエピソードがベースになっている。「丸の上手に書けたる子」は、「浮野」の作家ならではの作と思う。かな女の教えに〈俳句は、マルを描いて、それに立体感をつけて、自身はその影にそっと居るように表現すればよい〉があるからだ。幼子の描いた丸は絵の一部であったろうが、師の教えがまざまざと蘇った瞬間だ。「赤きマフラー」を手放さなかったのは作者ではなく夫に違いない、と思っていたら「買初めや赤と決めたる夫のもの」を見つけて思わずにやりとした。「椿を挿して心とす」は椿が季語以上の力を発揮している。秋子忌の作には、秋子らしい華やぎが備わり、在りし日の姿を偲ばせる。
蚊をつれて動物園を出でにけり
滑り台落花の中にとび出せり
初山河炎のいろの琴袋
膝掛けやすぐ眠くなる年を取る
浮かぶたび遠のいてゆく鳰
「蚊をつれて」のユーモア、「落花の中に」のスピード感、「炎のいろ」の激しさ、「年を取る」の自然体の潔さ、「遠のいてゆく」の確かな措辞。どれもみな小気味よい読後感に満たされて、特に好きな句だ。
美佐子さんは多くの旅をされてきた。
秋の夜や神を呼び出す笛太鼓(国東・高千穂)
納沙布の海霧に眉濃き夕べかな
城塞を海に傾け冬夕焼(イタリア)
潮騒かはた神集ふ水音か (出雲神社祭)
爽やかに靴音はづむシャンゼリゼ
フットワーク軽く、どこへでも出かけられるが、この行動力が美佐子さんの人生を作り上げてきたのだと思う。度々の引用になるが、「浮野」12月号の編集後記で〈一か月ほど前も、東京例会の後、突然日立海浜公園のコキアを見たいと宿も取らずにご夫妻で出かけていきました。相当歩かれたようです。〉と、龍野龍さんを心配させている。しかし、お二人は、これからもきっと、少し回りをはらはらさせながら自由自在に羽ばたかれることだろう。美佐子さんの作品に今後それがどう結実していくか、楽しみに拝見していたい。
利酒の良き名浮足立ちにけり
ほとんどお目にかかったことのない美佐子さんと、いつの日か酌み交わしたいものだ、とそんなことを考えてしまった。
辻村麻乃句集『るん』が「鳰の子」12月号で紹介されました!
『るん』辻村麻乃著 俳句アトラス
詩人の父と俳人の母を持つ作者は、詩の国からやってきたのではないかと思わせる自由で柔軟な発想で、独特な世界を詠んでいる。
春峰や深き森から海の音
電線の多きこの町蝶生まる
鞦韆をいくつ漕いだら生き返る
夏の雨耳石の破片漂うて
心の内を出したり抑えたりして
思春期や怒つた顔で薔薇を買ふ
爽やかや腹立つ人が隣の座
誰にどのような手紙を? ドラマに…。
夏帯に渡せぬままの手紙かな
尊父から娘に宛てた詩に対して
おお麻乃と言ふ父探す冬の駅
序にも跋にも詩的な言葉があふれている。
詩情豊かな句集に感謝。
1964年東京生まれ。
埼玉県朝霞在住。
1994年「篠」入会。
「篠」編集長、副主宰。
「ににん」創刊同人。
現代俳句協会会員。
執筆者:山口 登 「鳰の子」2018年12月号「句集に学ぶ」
日下野仁美編著『花暦吟行集』が「鳰の子」12月号で紹介されました!
『花暦吟行集』 日下野仁美編著 俳句アトラス
この吟行集は、「海」副主宰日下野仁美氏が「俳句はどのようにして作るの」という問いかけから立ち上げた、女性ばかりの吟行会「花暦」の平成18年から29年迄、130回に及ぶ全吟行の、参加者全員の一句と、吟行記を纏め掲載したものである。
眼前実景、即物具象の「海」の理念を念頭に歩んだ吟行会であったと日下野氏は述べておられるが、どの作品からも「俳句はこのようにして作る」と確実に成果が顕れ、歩きつづけ、詠みつづける意志と努力に感動の一書である。
日下野仁美氏の作品より
子規庵
身にしむや文字の乱るる仰臥録
高尾山火祭り祭
浄め塩踏みて火渡り始まれり
深大寺
薄氷の解けて流れに加われり
編者は、昭和22年生まれ。
平成3年「海」入会。
平成26年「海」主宰。
第4回俳句界受賞等、受賞歴多数。
執筆者:師岡洋子 「鳰の子」2018年12月号「句集に学ぶ」
小澤冗句集『ひとり遊び』が「門」12月号で紹介されました!
「門」(鈴木節子主宰)2018年12月号 風韻抄で、小澤冗句集『ひとり遊び』収録句が紹介されました。
龍の玉余生に悔いは残すまじ 冗
松本和枝(「雪解」同人)句集『釜鳴り』出来ました!

句集『釜鳴り』
『釜鳴り』(かまなり)
著者:松本和枝(まつもと・かずえ) 「雪解」同人 「雪解」選書358
一杓に鎮む釜鳴り炉の名残
皆吉爽雨の精神‟和楽交歓”の俳句を求めて
和枝さんの、「雪解」創始者・皆吉爽雨への思いは熱く、
師から学んだ写実に徹した叙情句は、
どの句にも温厚な人柄と芯の強さを感じます。
今後も素直に真直ぐに俳句の道を歩んでいただきたいと思います。
―古賀雪江「雪解」主宰―
【収録作品】より
涅槃図の灯に鳥獣を数へけり
蛭蓆沼の伝説封じ込め
師の句碑へ越の根雪を踏みにけり
文弥木偶黒衣の泳ぐ春の闇
芋の露こぼれて富士の影迫る
蒔絵師のうすき胡坐や火恋し
一陽来復仏の胸に杢の渦
鰤起し落石網の繋ぐ村
野に響く祝詞奏上虫供養
魚捌く血を滴らす養花天
【著者略歴】
松本 和枝
昭和17年 福井県生まれ
昭和49年 「雪解」入門、皆吉爽雨に師事
以後、井沢正江・茂惠一郎・古賀雪江先生に師事
現在、「雪解」同人・俳人協会会員
装丁 巖谷純介
印刷製本 中央精版印刷株式会社
私家版
刊行句集~落合美佐子(「浮野」同人)句集『野菊晴』出来ました!

句集『野菊晴』
『野菊晴』(のぎくばれ)
著者:落合美佐子(おちあい・みさこ) 「浮野」編集同人 (第三句集)
母ふたり健やかに老い野菊晴 美佐子
八十歳を迎えた自分史。
句集『野菊晴』。
『花菜』『野みち』に続く第三句集である。
長く「浮野」の編集を担当し、「浮野」の発展に尽くしている。
いつでもそばに俳句のあった生活を、明るく伸びやかに諷詠。
平凡な中に“詩”を見い出し、見える俳句を親しく確立している。
帯文(落合水尾「浮野」主宰)より
【収録作品】より
春遅々と点滴の点つもりけり
滑り台落花の中にとび出せり
コスモスや歩いて己確かむる
初山河炎のいろの琴袋
傍らは空大きくて草いきれ
若布刈舟海の青さを女神とす
飛花落花隠れやうなき主峰あり
風の蝶切に癒えよと利根を越す
さくらんぼ枝ごと光ごと貰ふ
来てるはず花人として見てるはず
恋猫となることもなく人を恋ふ
佛頭にとどまる落花二三片
【著者略歴】
落合美佐子(おちあい・みさこ)
昭和13年3月 埼玉県加須市に生まれる
昭和32年 「水明」に入会
昭和39年 「水明」を退会
昭和52年 「浮野」創刊と共に同人、編集に参加
昭和56年 埼玉俳句賞受賞
昭和61年 第1句集『花菜』出版
昭和62年 埼玉文芸賞準賞受賞
平成7年 第2句集『野みち』出版
平成11年 自註現代俳句シリーズ九期⑮『落合美佐子集』出版
「浮野」編集同人 俳人協会会員 埼玉県俳句連盟常任理事
お求めは俳句アトラスまで
定価 2,500円(税込)
村上鞆彦「南風」主宰~小澤冗句集『ひとり遊び』を読む
句集『ひとり遊び』を読む 村上鞆彦(「南風」主宰)
小澤冗さんと知遇を得たのは、俳句アトラスの代表である林誠司さんが中心となって運営していた同人誌「気球の会」であった。
本集にも「気球の会」に関する前書きの付いた句が収められている。
「気球の会」のメンバーで横須賀へ
浦賀水道帰燕の空の深みたる
この吟行に行ったのは、もう十年以上も前のことになる。
「気球の会」はその後、ひとまずの役目を終えて解散したが、数名のメンバーで句会は続けていた。
誠司さん、冗さん、日下野由季さん、私……、毎月早稲田の小さな会議室に集まっていたころが懐かしい。
その句会も自然と消滅し、近年は冗さんにお会いすることもほとんどなかったが、このたび上梓された『ひとり遊び』を手にしてみて、ふたたび冗さんの気さくな笑顔に触れたようで嬉しくなった。
以下、私の注目した句について述べてみたい。
一病は一芸のうち実南天
冗さんは、心臓にペースメーカーを入れておられる。
この句の「一病」とはその心臓の病のことだろう。
それを「一芸のうち」と笑いに転じてみせた胆力は流石と思う。
「実南天」の充実した赤色が艶々と美しい。
昼寝覚余生の貌をなでまはす
昼寝から覚めたばかり、まだ意識にはどこか濁りが残っている。
それを拭うように、顔を撫でる。
「余生の貌」にはどこかとぼけたような飄逸味があり、また「なでまはす」はいかにも人間臭い表現で面白い。
一叢はますほの芒罔象女
「ますほの芒」とは、真赭(ますほ)の色、つまりやや赤味を帯びた芒のことを言い、「罔象女」とは、水をつかさどる女神のことを言う。
句意は、野のひとところに、周りとは違う色の芒を見つけた。
そのとき、ふと女神の存在を直感したというふうに解したい。
「ますほ」の色彩から女神を思うその優しい感覚と、余計なもののない簡潔な表現が印象的な一句である。
礁荒る能登金剛の新松子
能登の旅吟だろう。
荒磯の光景に配した「新松子」の青さが匂い立つようで、初々しい詩情を生んでいる。
「能登金剛」の重々しい響きと「新松子」の清新さが好対照をなしている。
石ひとつ積めば下北雪が降る
津軽の風土を詠った句が散見されるのは、津軽が奥様の故郷だったからだろう。
この句、「石ひとつ積めば」から「下北雪が降る」への転換がドラマチック。
石を積むというと、賽の河原がまず思われるので何となく寒々しい感じがするが、その印象を援用しつつ、読み手を一気に下北の雪景色のなかへと誘ってゆく表現の呼吸が見事である。
ひよどりの初声にしていつもの木
元日、鵯が鳴いている。ときに耳に障る声ではあるが、正月気分のなかで聞くと、めでたく晴れやかな声に思える。
その鵯がいるのが「いつもの木」であるという点がこの句の眼目。
日常的であること、普通であることのよろしさをよく知っている作者なのである。「いつもの木」という構えのない口語がさらりと使われて効果を出している。
ところで、本集を読んでいると、前書きの付いた追悼句が随所に見られることに気づく。
その対象は、兄、義父、義母、義兄といった身内はもちろん、俳句の師や句友、尊敬する俳人まで、幅広い人々に亘っている。
このことは、冗さんの几帳面さ、義理堅さをよく物語っていると思う。
お世話になった大切な方々の死に際し、心を込めた一句を手向け、深い祈りを捧げる。
それだけではなく、その句を句集に録し、活字にして、あらためて哀悼の証とする。死者から受けた恩を忘れぬためという自分自身へ向けての意味もあるだろう。
冗さんは本当に義に厚い方なのである。
なかでも追悼句の最たるものは、奥様へ向けてのものである。
平成二十七年三月三十一日、妻・榮子逝く 享年七十四
旅立ちを一と日違へし四月馬鹿
あと一日違ったならば、翌日は四月一日でエープリルフール、すべてを嘘として流せたかもしれないのに……。
無益とはわかっていても、ふとそんなことを考えてしまう、という句意に読める。
句の内面には深い悲しみが潜んでいるのに、表面はそれを悟らせぬような飄々とした軽い口ぶりで仕上げている。
冗さんなりの男の含羞というものだろう。
奥様を亡くしたあと、ひとりとなった冗さんの寂しさはいかばかりのものだったろう。
〈亡き妻の部屋を灯して去年今年(147)〉という句も見える。
しかし、ひとつ明るい材料があるとすれば、それは「娘」さんの存在である。
「娘」さんを詠んだ句は、句集の冒頭から奥様への追悼句が掲載された頁までは、ほとんど見られない。
ところが、奥様への追悼句以降、「娘」という言葉は頻繁に冗さんの句に出てくるのである。
八月や娘らの声する妻の部屋
夏休みで、娘さん一家が冗さんの家に泊まりにきているのである。
以前は灯りをともしてもがらんとしてむなしいだけだった「妻の部屋」に、今日は娘さん一家の賑やかな声が満ちている。
それを聴きながら安らいでいる冗さんの莞爾とした表情が想像される。
最後に、これからの冗さんが娘さんや句友のみなさんに支えられつつ、お元気で俳句を続けてゆかれるよう心からお祈りしている。
いつかまた句会をご一緒できる機会があれば幸いである。
加藤房子句集『須臾の夢』が「朴の花」第104号で紹介されました!
加藤房子句集『須臾の夢』
平成30年6月 俳句アトラス刊
夜空をイメージする濃紺に、夢を表現しているかのように浮かぶ水玉、装丁、装画の美しさに魅了される。
「須臾」、とは暫時少しの間、しばらくの間の古語で水玉はそれぞれの夢というようにとらえた。
作者は、薬剤師の仕事を続け母の介護、夫の介護と見送りの中で、自分自身の病気という状況下で鋭い観察による詩情豊かな美しい句が詠まれている。
晦日蕎麦過去も未来も須臾の夢
落されし生命鮮やか桃摘花
行間に青き残夢や遠花火
蓮根の糸を頼りの余命編む
落日の遺影に真紅の薔薇を百
作者は生きた証として娘や息子に残すべくこの句集を纏めたと書いておられる。
今後も鋭敏な詩性と抒情ある句を楽しみに「須臾の夢」のつづきを期待している。
楽しとは生涯未完亀鳴けり
―俳句とエッセイ「朴の花」第104号~新刊俳書紹介 執筆・朝久野みち子