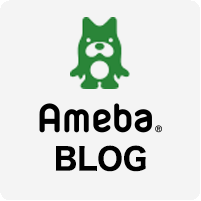1951年9月14日東京生まれ。
俳句を森澄雄、小林康治、中村俊定に学ぶ。
「林」創刊より参加、小林康治に師事。
俳人協会会員、俳文学会会員。
句集『寒オリオン』は、作者の第四句集にあたる。
あとがきで、冬の星座は美しい、中でもオリオン座が好きと書いてある。
このことは作者のお人柄、句柄に通ずる気がする。
平明な中の品格、静かな表現の奥に感じられる作者の強く澄んだ意志。
そして、対象に対する眼差しの優しさに心惹かれる。
大杉を見に炎天の大花野
葉桜や飾るものなき略年譜
冬椿飾らぬ人の最も艶
掌の中の家宮氷の冷たさに
土偶まだ眠たき眼楤芽吹く
新年の曲は渦巻くワルツより
犬猫の厄年いくつ式部の実
左義長の炎の先の男女神
冬菫木漏れ日を得て意志の色
(2019年7月30日刊 俳句アトラス)
―「残心」2019年第17号 受贈句集より(執筆・西田啓子)―
加藤房子著『須臾の夢』
集中「八咫烏」の項の中では、
山上の一樹序の舞紅枝垂桜
西行の命終の夜の花あかり
地の魑魅呼びて変化の老枝垂桜
と、桜花の美しさと、観る位置によっては妖艶とも映る様が詠まれている。
「生成り女」の項では、
遺影いま考の声降る春の星
母逝きしあとの闇夜を桜狩
と、父へ母への深い思慕の念が詠まれ、「狐雨」の項の中では、
天の声地の声舞楽始めかな
忘却の闇に齢古る雛ならむ
月へ飛ぶロケット野心青々と
と、舞楽と雛の雅を詠む一方、科学的な言葉を採った句も散見され、楽しめた。
また、「張子の兎」の項の中では、
玄室の朱雀を犯す黴の糸
惜命の朝の茜や神帰る
と、歴史に纏わる世界へと誘う句に出会え、四項の「風来坊」の中では、
音もなく一病と棲む春障子
一病は余生の福音大旦
半夏生すでに白旗身の内に
など、病を克服し、その後の日常を明るさをもって詠まれており、最後には、
楽しとは生涯未完亀鳴けり
と、泰然とした心境を吐露し、結んでいる。
著者の益々御健勝を祈念します。
―「繪硝子」2019年2月号 「句集を読む」(執筆・平野暢行)―
加藤房子句集『須臾の夢』
白梟首をぐるりと月隠す
たかんなの雨後の育ちの下剋上
晦日蕎麦過去も未来も須臾の夢
一句目の下五での転換の面白さ、二句目のエネルギッシュなリズム感、三句目のもう一人の自分を見つめる冷静さ等作品は多彩。
二十年ぶりの第二句集。
桐一葉母の命の澄みてきし
白骨の余熱は未練冬の薔薇
生も死も影の相寄る大干潟
音もなく一病と棲む春障子
蛤になる後ろ指さされても
この間、母上の看取りとご主人の看取りに加えてご自身も癌の手術を受けられたとのこと。
母上の最後のご様子が見て取れる一句目。
二、三句目からはご主人を亡くされた衝撃を受け止めようとする前向きさが伝わってくる。
四句目は現在を受け容れる作者の姿が美しい。
この覚悟が五句目だろう。
掉尾の、
楽しとは生涯未完亀鳴けり
が力強い。
―「雲取」2019年2月号 「句集・俳書存問」(執筆・物江里人)―
落合美佐子句集『野菊晴』(俳句アトラス)
「浮野」(落合水尾主宰)同人。
句集『花菜』『野みち』に続く第三句集。
平成7年から平成30年までの句を収録。
句集名は次句、
母ふたり健やかに老い野菊晴
主宰は帯文で「いつもそばに俳句のあった生活を、明るく伸びやかに諷詠。平凡の中に詩を見出し、見える俳句を親しく確立している」と賛。
飛花落花隠れやうなき主峰あり
白梅や痛みを解きて逝き給ふ
膝掛やすぐ眠くなる年を取る
―「耕」33周年記念号 「句集紹介」(執筆・和出 昇)―
昭和2年千葉県生まれ、同57年「蘭」入会、平成5年「蘭」同人。
名誉主宰・松浦加古氏の序によれば、作者は、野澤節子健在の頃の「蘭」に入会した最古参の一人。
現在91歳。
この句集のメインテーマは、
(1)生涯の文芸の師と仰ぐ野澤節子への格別の思慕
(2)作者の住む成田市名古屋の風景、とりわけ作者の自宅の前にある小御門神社も美しい聖域
(3)夫との生活、更に夫亡きあとの思慕
の三つである。
句集名「東路」、作者の先祖がその創建に携わった「小御門神社」のご祭神・太政大臣藤原師賢の歌、
東路やとこよの外に旅寝して憂き身はさそな思ふ行く末
に因む。
句集帯掲載句より十句
利根川を去るきつかけの嚏かな
白鳥引く藍の深きを湖に置き
われに添ふ師の影さくら咲きてより
亡き夫に謝すことばかり天の川
障子貼りこの明るさに一人棲む
待つといふ心の張りや牡丹の芽
影もまた匂うてをりぬ梅林
身に入むやおはすごと置く男靴
二度訣かるる思ひに捨つる白絣
星月夜あふぎ逢ひたき人あまた
(俳句アトラス 2,315円)
―「海」2019年9月号 「新刊句集紹介」(執筆・後藤勝久)―
家族とも裸族ともなり冷奴 辻村 麻乃
働かぬ蟻ゐて駅前喫茶店
嫉妬てふ限りなきものサングラス
辻村麻乃句集『るん』 俳句アトラス刊
第二句集。「篠」主宰。
『るん』はルンという言葉の概念に依る。
詩人の岡田隆彦、俳人の岡田史乃の間に生まれ、新しい風を吹いても良いのではと思うようになったと。
発想がどこへ跳んでゆくか予測出来ない作家である。
一句目、クーラーが普及する以前の典型的な日本の夏。
夕焼空、豆腐屋のラッパ、蚊取線香。
ステテコやアッパパ姿の家族で囲む夕餉。
冷奴の涼しさと、たっぷりの会話もこれ以上なきご馳走。
「家族」「裸族」のリズムが楽しい一句。
二句目、茹だるような真夏の昼間。
冷房の効いた喫茶店で束の間の休息を取るサラリーマン諸氏。
個々の集まりが大きな群となり、やがて堅固な社会を作り上げてゆく過程の中、次のステップへのエネルギーを蓄える貴重な時間。
身近な蟻に譬え、少々の揶揄を込めた励ましの句と受け取れる。
三句目、ハートのある生物にとって逃れられないネガティブな感情。
善悪、教養の有無に関係なく、軽いものから根深いものまで、置かれた立場により千差万別。
忌わしいイジメも嫉妬が発端という。
回避は困難だが、まず他との比較をやめ、努めてやるべき事に集中する。
猶且つ、煩悩に苛まれるなら、嫉妬の炎に燃える眼を洒落たシャネルやレイバンのサングラスに閉じ込め、真夏の太陽に身を焦がせよう。
―「枻」令和元年9月号「現代俳句を読む」(執筆・高成田満里子)―
烏瓜不器用にして装へる 福島たけし 句集『寒オリオン』
ふるまひは地酒地魚浦祭 新谷壯夫 句集『山 懐』
―「沖」2019年9月号 「沖の沖」(能村研三・抽出)―
人声をただ音と聞き秋の旅 福島たけし
(ひとごえを ただおとときき あきのたび)
旅とは何かを通過すること。
人々の話し声をただ音として聞きながら、その街を通り過ぎてゆく。
人間のおしゃべりは音と意味でできているが、意味がわからなければ音のみ。
音楽や小鳥のさえずりと同じ。
句集『寒オリオン』から。
‐讀賣新聞令和元年8月20日(火) 長谷川 櫂「四季」―
猫の尾のふれて弾ける鳳仙花 新谷 壯夫
(ねこのおの ふれてはじける ほうせんか)
鳳仙花の実は成熟すると勢いよく割れて内包された種が四散する。
この仕組みはスミレなどにも見られ、広範囲に増殖するための構造である。
割れた皮がくるりと捲(ま)き上がることで指で弾いた状態となり、1メートル先まで飛ぶこともある。
無遠慮な猫の尾が触れればその衝撃で弾け、猫の体に付いてさらに遠くまで運ばれるのだから、植物の巧みな手段にあらためて感心する。「鳰の子」同人。
―愛媛新聞令和元年8月20日(火) 土肥あき子「季のうた」―