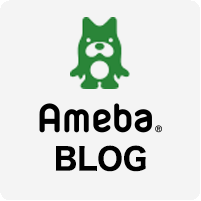さまざまの赤き実のある十二月 森 澄雄(もり・すみお)
いわれてみればそうだと思う。
南天の実、一位の実、青木の実、みな赤い。
最近では街路樹のアメリカ花水木の赤い実や、庭のピラカンサなども赤い実をつける。
あたりが冬ざれてゆく中、これらの実はどこか、寒さを和らげてくれてる温かみを覚える。
松尾芭蕉の句に、
菊のあと大根の外更になし
(きくのあと だいこんのほか さらになし)
がある。
菊のあとには大した花はない…、というが大根の花があるではないか、と言っている。
今の私たちは、外国から入って来たシクラメンやポインセチアなど、冬でも眼を楽しませてくれる植物に囲まれている。
しかし、芭蕉の句のように、昔は菊など、秋の花が終われば、春になるまで「これ」という花はなかったようだ。
さぞ殺風景であっただろう。
それはそれで良かったのか、今のほうがいいのか、それは個人の考えだろう。
澄雄さんの句がいいのは、寒々とした中に「あたたかみ」を見い出していること。
俳句を作ることを「ひねる」という。
これは俳句特有の言い回しで俳句の特性をよく表している。
小説をひねる
詩をひねる
短歌をひねる
とは言わない。
俳句だけが「ひねる」ものなのだ。
聖から俗(またはその逆)
静から動
明から暗
などのように…。
この句は、
明から暗
暖から寒
と言えよう。
寒いからと言って、閉じこもっておらず、積極的に生命の息吹を感じる。
澄雄さんといえば近江吟が有名。
澄雄さんは晩年、寝たきりになっても近江を思い、近江を詠った。
風景に触れることは命に触れることである。
澄雄さんの句にはそれを生涯貫いている。