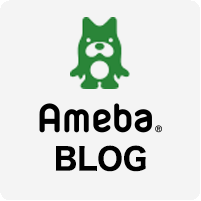矢印の最後は空へ冬桜 渡邉 美保(わたなべ・みほ)
作者は第29回俳壇賞を受賞している。
しっかりとした写生力を底力に、
けむり茸踏んで花野のど真ん中
すかんぽの中のすつぱき空気かな
拾ひたる昼の蛍を裏返す
割るためにバケツから出す薄氷
紋白蝶呼んで弁当開きけり
など、多彩な作品を展開している。
掲句。
清らかで、のびのびとした感性が冴える作品。
公園などの散策風景であろう。
「順路」などを示した「→」に沿って進んでゆくと、最後は「↑」…。
つまり、最後は「天」を指して終わっていた…、というのだ。
誰かが「いたずら」をした、と考えてもいいが、それでは面白くない。
これは「虚」、つまり「文学的虚」と考えるべきである。
ここに作者の詩の世界の柔軟さを見ることが出来る。
一部、いや、多くの俳人が、今もって「虚」を軽んじ、嫌うのは残念なことである。
「虚」と「嘘」を混同している。
「虚」こそ、古代より詩歌人の美意識、詩精神が作りあげて来たものではないか。
大和の神々、京のもののけ、鎌倉の怨霊…、これらはみな先人たちが作り上げて来た「虚」である。
神々しい清らかな風景に出会った時、神を感じ、周囲1メートルしかない夜の灯りの他はすべてもののけが支配していると信じ、切通を抜ける風や竹藪の音に無念で散ったもののふの憾みの声を聞く。
これらはすべて先人たちの感性が作り上げた虚である。
もし、私たちの世界、特に文学世界の中に「虚」がなければ、どれほど貧しくつまらないものかを考えてみるといい。
「源氏物語」だって「おくのほそ道」だって大いなる虚である。
ここはそのまま、まるで神の啓示のごとく矢印が「天」を向いていた、と考えるべきである。
季語「冬桜」もいい。
冬の抜けてゆくような青空が見えるからだ。
輝くような青空の中にかすかに震える冬桜の白が神々しい。
俳句…というか、日本の文学には「虚に遊ぶ」という心が必要であることを示した一句と言えよう。