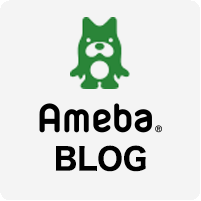誰彼もあらず一天自尊の秋 飯田蛇笏
(たれかれも あらず いってん じそんのあき)
蛇笏77歳での作。
この年に蛇笏は亡くなったので、ある意味、辞世の句と考えてもいい。
「秋の天」を詠んだ句で、これほど格調高く、抜けるような秋の青空を詠んだものは他にない。
「一天」というのがいい。
例えば、これを「青空」「大空」とかに変えてみても一句としては成り立つ。
しかし、この漢詩的表現である「一天」が格調高く、硬質な響きが一句に満ちている。
「青空」や「大空」では詩的空間が「横」に広がってしまうが、「一天」は「縦」に貫いてゆくような鋭さがある。
それが「秋」にはよく似合うと思うのである。
さらに言えば「自尊の秋」もいい。
「自尊」とは「自分を尊ぶ」ということ。
蛇笏の生涯を見れば、この、尊ぶ心が、世俗的・権勢的なものではないことは明らかである。
ひたすら生きた
さらに言えば、
ただただ俳句のために生きた
自分の生涯を高らかに肯定しているのである。
ところで、この句。
厳密に考えると、どういう意味かいまいちわからない部分もある。
「誰彼もあらず」とはどういう意味か?
誰も彼もいない
つまり、
誰もいない
という意味あいで考えれば、蛇笏の生涯を過ぎ去っていった人々、そういう人々が今はもうこの世にいない、あるいは、自分の傍にもういない、ということになろう。
ただ、こうとも考えられる。
誰でも彼でも関係ない
つまり、
自分は自分である。
という考え。
信じた道、信じた俳句の道をひたすら進むだけだ。
という自負である。
自尊の秋
ということを考えれば、後者であろう。
ただ、蛇笏最晩年の句と考えれば前者の意味もあろう。
つまり、この場合、両方の意味があると考えていいのではないか。
死を意識した蛇笏の胸中には、なつかしい人々の面影があっただろう。
「一天」とは残された自分の寂しさのような気もする。
そして、おのがひたむきに生き、俳句に賭けた人生を振り返っただろう。
この場合、「一天」は自分の人生の象徴にもなるだろう。
この二つの思いが、
誰彼もあらず
という言葉を生み出したのではないか。
そして、その命をいとおしむ心が「自尊の秋」である。
最晩年になっても、これほどの力強く、すがすがしい一句を生み出した、蛇笏の気力はすさまじい。
蛇笏翁、面目躍如の一句である。