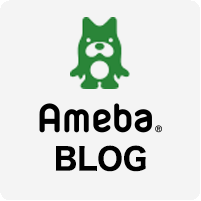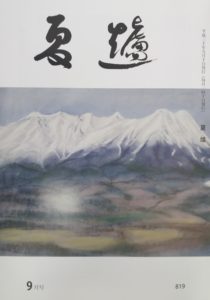
「夏爐」819号(平成30年9月号)
「夏爐」819号(平成30年9月号)
主宰 古田紀一 編集人 古田紀一
結社誌・月刊・通巻819号・長野県諏訪郡下諏訪町・創刊 木村蕪城
長野県には意外と結社が多い。
豊かで清々しい信州の大自然が身近にあるからだろうか。
その中でも「夏爐」は長野随一の伝統結社である。
「夏爐」については創刊主宰の木村蕪城を語らないわけにはいかない。
蕪城は大正2年鳥取県に生まれ、「ホトトギス」「夏草」などで俳句を学んだ。
それゆえ「夏爐」は師系に高浜虚子、山口青邨を掲げている。
昭和17年に「夏爐」を創刊した。
おるがんの鳴らぬ鍵ある夜学かな
きさらぎや白うよどめる瓶の蜜
一茶の像ちひさしこれに鏡餅
冬海のかなた日当たる八束郡
夏炉ありほそぼそとしてわがたつき
天龍のひびける闇の凍豆腐
寒泉に一勺を置き一戸あり
母みとる未明の銀河懸るなり
法華経の一品を手に花疲
郭公の声のあけくれ吾子育つ
「夏爐」は蕪城が好んで使った季語だと記憶している。
いかにも山国・諏訪の風土を活写している。
私は当初、松尾芭蕉の言葉とされている、
予(よ)が風雅(ふうが)は夏炉冬扇(かろとうせん)のごとし
から来ているのだろうと思って、古田主宰に聞いてみたことがある。
「夏炉冬扇」とは、字のごとく、「夏の囲炉裏、冬の扇」でつまり、
何の役にも立たないもの
ということである。
もちろん、この言葉には、それだけではない、芭蕉の強烈な自負もある。
総合的に考えると、「夏炉」という季語を好んで詠んだこと、諏訪という風土、そして、芭蕉の言葉から生まれたのではないか。
現主宰の古田さんは、平成16年蕪城逝去により、第二代主宰となった。
木村蕪城は教師であり、古田主宰はその教え子である。
学校卒業も何くれと世話になり、当時はむしろ詩のほうに興味があったが、そういう蕪城の人柄に魅せられ俳句を始めた。
この号で通巻819号…、私は蕪城にお会いしたことはないが、古田主宰と話したり、「夏爐」を読む度、俳縁の厚みというものを感じる。
俳句というのはわりと「俗」な部分が多い。
それは別の言い方で言うと、他の文芸より「人間臭い」とも言える。
蕪城を慕い、その功績を残そうと奮迅する古田主宰の姿を見ると、俳句の師というだけではない、濃密な情を感じる。
俳句の世界における人間臭さは時に悪い面、醜い面もあり、それが現在の結社制度の限界を招いていると私は考察するが、「夏爐」にはそういうものがない。
むしろこの師弟関係にはあたたかで、切なささえ感じる。
主宰作品「円座」より
ともがらの墓探し当つ草の王
豆腐屋は野辺の三叉路夏めける
みな海を見つめて梅雨に入りけり
砂にわが足跡しるす大南風
よく噎せる齢冷酒に冷水に
「草の王」とはケシ科の一年草で、夏に黄色い花を咲かせる。
神奈川県鎌倉で行った夏季鍛錬会の報告記事が掲載されていたので、3句目4句目はその折の作であろう。
シンプルな表現でありながら、情がこまやかで深みを感じる。
こまかいところだが、
砂にわが足跡しるす大南風
は、普通の人であれば、「しるす」ではなく「残す」としてしまうのではないか。
砂にわが足跡残す大南風
これでは「情」にもたれかかっているし、流行曲のようだ。
「残す」は「写生」ではなく「報告」なのだ。
「しるす」が「写生」であり、「情」に流されず「詩」となるのだ。
こまかいところ…と言ったが、俳句に於いてこの「情」に流されない、ということは非常に大事で、「写生」の効用は、風景をしっかり描き、「詩」をにじませることにある。
「今月の十句」および会員作品「山河集」より
鮒鮓や風鎮ゆらす風よろし 長井紀子
根こそぎのもの流れつく梅雨の花 景山みどり
冷房を薬臭の航く長廊下 中村鈍石
掌握の力の萎えし瓜をもむ 崎 多瑠子
丸かじりに塩派砂糖派トマト捥ぐ 梅野啓子
家ずらす工事溽暑を幾日ぞ 荻野芳子
足病むや願の糸の墨を濃く 山本うめ
笹舟を梅雨の大河が飲み込める 市川あきら
京びいき何がなんでも貴船川床 織田ひでを
恋猫が鳴き鳴き歩く駐車場 小松美左子
生業としての小塾韮の花 鈴木 岬
どの句も生活・風土に根ざし、そこから詩が生まれていることに感嘆した。
「おきれいな俳句」は一つもない。
自然詠でも、そこに生活、さらにいえば人生が潜んでいる。
「丸かじりに」の句を「今月の十句」に選ぶ古田主宰の選句の姿勢に敬意を持った。
俳句は文学であるか否か、芸術であるか否か、という話はいまだに出る。
私はこう思う。
俳句は芸術的なものからそうでないもの、尊いものからそうでないもの、聖から俗、自然から生活、花鳥諷詠から滑稽まで、すべてを包み込んでいる大きな文学だと。
古田主宰の選句を見ていると、きっと彼もそういう考えなのではないか、と感じた。