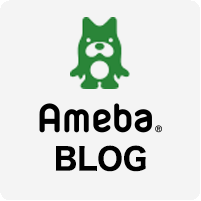芭蕉忌や遅れ生まれし二百年 野村喜舟(のむら・きしゅう)
(ばしょうきや おくれうまれし にひゃくねん)
松尾芭蕉が亡くなったのは元禄7年10月12日。
新暦では11月29日であった。
そして今年は11月19日…つまり「今日」が芭蕉忌である。
松尾芭蕉が凄いことは誰もが知っているが、では、いったいどんな功績があるのだろうと考えると、答えられる人は少ないのではないか。
もちろん様々あるが、私は、
かるみの実践
と、
高悟帰俗(こうごきぞく)の実践
にある、と考える。
まず「かるみ」だが、簡単に言えば、
和歌、漢詩、諺などにもたれかからず「17音」で独立した「詩の世界」を完成させた。
ということである。
(「かるみ」については二説あり、そういうものではなく、「軽々とした詩境」をいうのである、という説もあるが、その説は私は取らない。)
芭蕉以前の俳諧は「和歌」「漢詩」「諺」などを念頭とし、それをひねった…つまり茶化した言葉遊びの文学だった。
芭蕉の、
古池や蛙飛び込む水の音
は、最初「蛙飛び込む水の音」だけが出来、上五に悩んでいた。
一番弟子の宝井其角は「山吹や」を提案した。
山吹や蛙飛び込む水の音
其角の意図は、
かはづなくゐでの山吹ちりにけり花のさかりにあはまし物を よみ人しらず
都人きてもをらなむ蛙なくあがたのゐどの山ぶきのはな 橘公平女
忍びかねなきて蛙の惜むをもしらずうつろふ山吹のはな よみ人しらず
澤水に蛙なくなり山吹のうつらふかげやそこにみゆらむ よみ人しらず
みがくれてすだく蛙の諸聲に騒ぎぞわたる井手のうき草 良暹法師
沼水に蛙なくなりむべしこそきしの山吹さかりなりけれ 大貳高遠
山吹の花咲きにけり蛙なく井手のさと人いまやとはまし 藤原基俊
九重に八重やまぶきをうつしては井手の蛙の心をぞくむ 二條太皇太后宮肥後
山吹の花のつまとはきかねども移ろふなべになく蛙かな 藤原清輔朝臣
かはづなくかみなびがはにかげみえていまかさくらん山ぶきの花 厚見王
あしびきの山ぶきの花ちりにけり井でのかはづはいまやなくらん 藤原興風
など、和歌では「山吹」と「蛙鳴く」は「セット」だったのだ。
其角はそれを踏まえ、
あらら、この蛙は鳴かないで、水に飛び込んじゃったよ!
と「パロディ」にして見せたのである。
このことからも「俳諧」は「和歌」のパロディであったことがある。
私はこの取り合わせに其角の切れ味を感じるが、ご承知の通り、芭蕉は、それを採用せず、ただ、
古池や
とした。
これが「和歌」「漢詩」などのアンチテーゼから脱却した「蕉風俳諧開眼」の瞬間である。
もう一つの「高悟帰俗」。
これは芭蕉の言葉、
高く心を悟りて俗に帰るべし(服部土芳『三冊子』より)
という俳諧精神の確立である、
俳諧の本質は、
雅俗混合(がぞくこんごう)
である。
一句の中に「雅なもの」「俗なもの」とが混在していることである。
「おきれいごとだけではいけない」「俗なだけではいけない」ということである。
詩心は常に高く、しかし、俳諧に詠む題材は「俗」から離れてはいけない。
ということである。
これが、雅な「やまとことば」で「雅な世界」を詠う「和歌」と一線を画しているのである。
極端に言えば、和歌は「うぐいす」は詠うが、「犬の糞」などは詠わない。
雅ではないからである。
しかし、俳諧は「うぐいす」も詠えば「犬の糞」も詠う。
そして、それを「詩」にしてみせる。
これが「俳諧」の素晴らしさ、芭蕉俳諧の素晴らしさである。
昨今、俳諧、俳句における「アニミズム」が注目されているが、「アニミズム」とは簡単に言えば、
あらゆるものに神聖なものを見い出す姿勢
である。
美しいもの、美しくないもの、高貴なもの、俗なもの、すべて「平等」に生命の尊さ、輝きがあるという考えだ。
すべて平等に生命の尊さを認め、詩としての「美」を見い出したのが芭蕉であった。
さて、掲句。
野村喜舟(明治19年(1886)~昭和58年(1983))は石川県金沢市生まれ。
本名は喜久二(きくじ)。
幼児期に東京に移り浅草、小石川に住んだ。
小石川砲兵工廠に就職し、転勤の為、福岡県小倉(現・北九州市小倉区)に移住し、終戦とともに退職し、以後は小倉に住んだ。
42年より夏目漱石門下の松根東洋城の指導を受け、東洋城の「渋柿」創刊時に課題詠選者として参加している。
昭和27年、東洋城引退後の「渋柿」主宰に就任。
同じく伝統俳句を標榜する高浜虚子の「ホトトギス」とは一線を画し、〝松尾芭蕉直結〟の精神を提唱した東洋城の意志を継ぎ、活躍した。
東洋城が雄大な風景句を得意としたのに対し、生活や人情などの人事句の名手、連句の名手として知られる。
句集に『小石川』『紫川』『喜舟千句集』などがある。
私は、喜舟は、久保田万太郎と並ぶ俳句の天才だと思っている。
この人のことはもっともっと顕彰されていい。
「二百年」というのが面白い。
芭蕉が生まれたのが寛永21年(1644)、喜舟が生まれたのが明治19年(1886)、だいたいの「200年」である。
私もそうだが、多くの俳人にとって芭蕉は永遠の憧憬である。
喜舟だったら芭蕉先生も舌を巻くような作品を作ったに違いない。
「遅れ生まれし」にはそんな喜舟の自負ものぞけるが、「200年」というのが味噌で、そんなに遅れて生まれてはどうにもならない…というユーモアがあるだろう。
茶目っ気と言ってもいい。
正岡子規、高濱虚子の「ホトトギス」とは一線を画し、「芭蕉直結」…芭蕉の俳句をただひたすら目指したのが、「渋柿」派の俳句であり、喜舟の師・松根東洋城の俳句であり、喜舟の俳句である。
私はこの人は「かるみ」最後の人だと思っている。
久保田万太郎も草間時彦などにも「かるみ」の傾向は見られるが、芭蕉の「かるみ」とは少し違う。
喜舟の「かるみ」は芭蕉の「かるみ」そのままであるように思える。
今年は芭蕉が亡くなって325年である。