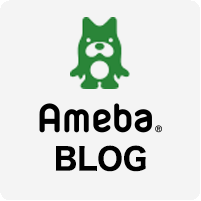あづまはや根の国へ振る夏帽子 加藤房子(かとう・ふさこ)
(あずまはや ねのくににふる なつぼうし)
「千種」代表。
昭和9年、横浜育ち。「風花」「蘭」を経て、小枝秀穂女に師事。
昭和63年、小枝秀穂女創刊の「秀」に参加。秀賞を二度受賞。
平成19年「秀」終刊に伴い、翌年「千種」創刊、代表を務める。
今年、「千種」創刊10周年、第二句集『須臾の夢』(俳句アトラス刊)上梓。
「あづまはや」がこの句の眼目となる。
この言葉は「古事記」「日本書紀」に出てくるヤマトタケルの言葉。
「吾妻(あづま)はや」…、つまり「ああ、わが妻は…(もういないのだ!)」という意味である。
エピソードを要約して紹介しよう。
ヤマトタケルは、父の景行天皇の命で、大和朝廷に従わない者たちの討伐を命じられ、九州を平定し、出雲を平定し、東国を平定した。
東国平定の際、今の神奈川県横須賀市にさしかかり、小船で海を渡り、今の千葉県へ渡ろうとした。
今の東京湾である。ヤマトタケルは東京湾を眺め、
「なんて小さな海だ。ここなどは一っ跳びに渡れるだろう」
と言った。
それを聞いた、この地の「海の神」が激しく怒り、小舟が海の真ん中にさしかかった時、暴風雨を巻き起こした。
船が今にも転覆しそうな時、タケルの妻・弟橘媛(おとたちばなひめ)が、
「海神のお怒りを鎮めるため、私が身を捧げます」
というや否や、海に身を投げた。
海はたちまち穏やかになった。
ここは今、「浦賀水道」、古名を「走水」(はしりみず)という。
その後、東国平定を終え、大和へ帰還するタケルは、「古事記」では今の神奈川県足柄峠、「日本書紀」では群馬碓氷峠あたりで、何度も東の方角を振り返り、
「吾妻はや」
と、弟橘媛を偲んだ、という。
(ちなみに、それゆえ「関東」のことを「吾妻」という。)
掲句の鑑賞に戻る。
つまり「あづまはや」とは、愛する人への慟哭の言葉。
この場合、配偶者と限定する必要はないだろう。
自分にとって心から愛する人、亡くなったその人への慟哭の言葉である。
「根の国」とは「死者の国」。
作者は、愛する人が住む黄泉の国へ夏帽子を振っているのだ。
「夏帽子」も、この句に切なく、あたたかな郷愁を添えている。
なんとなく、私は西条八十の詩を思った。
母さん、僕のあの帽子、どうしたんでせうね?
ええ、夏、碓氷から霧積へゆくみちで、
谷底へ落としたあの麦わら帽子ですよ。
母さん、あれは好きな帽子でしたよ、
僕はあのときずいぶんくやしかった、だけど、いきなり風が吹いてきたもんだから。(以下、略)
「夏帽子」は郷愁、思い出の象徴である。
この句は観念句であるが、虚の世界から実へと迫っている。
観念から、自己の内面、別れ、という「実」を表現しているのだ。
松尾芭蕉も、
虚に居て実を行ふべし
と言っている。
実景よりも激しい、心の奥底で生み出した「慟哭」の一句、と言えるだろう。