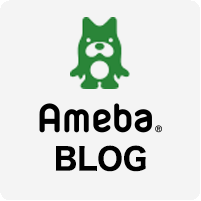つかれた脚へとんぼとまつた 種田山頭火
(つかれたあしへ とんぼ とまった)
最近まで、蝉がうるさいほどに鳴いていたが、彼らもあっという間に姿を消し、ふと、耳を澄ますと、秋の虫たちの声で満ちている。
「虫」という存在は一般的に人に好かれる存在でない。
毛虫、カメムシ、ゴキブリ…、みな「嫌われ者」だ。
黄金虫などは私が知る限り、何の害もない虫だが、見ていて気持のいいものでもない。
蟋蟀でさえ、音色を聞く分にはいいが、実際、そばにいると気持のいいものではない。
俳人で、ふと「虫」を好んで詠んだのは誰だろう…、と考えたら、なんとなく「山頭火」の名が思い浮かんだ。
一茶も小さな命を愛し、共感したが、あまり「虫」というイメージはない。
もっとも、
やれ打つな蠅が手をすり足をする 一茶
がある。
が、どちらかというと「馬」とか「蛙」とか「雀」とか…、そういう印象がある。
山頭火(明治15年(1882)~昭和15年(1940))は山口県佐波郡(現・防府市)の大地主の長男として生まれた。
11歳の時、母が自宅の井戸に投身自殺をした。
これが山頭火の俳人としての道…、というより運命そのものを決定した。
15歳から俳句を始めた。
早稲田大学文学科に入学したが、神経衰弱の為、退学し防府に戻る。
父とともに酒造業を経営したが、父は女狂い、山頭火は酒狂いだから、身上はあっという間に傾いた。
28歳で佐藤サキノと結婚し、翌年には長男が誕生。
32歳の時、荻原井泉水に師事し、「層雲」に参加。
35歳 の時、「層雲」選者の一人となり、めきめき頭角を顕したが、その頃に種田家は破産、父は行方不明となり、夫婦は熊本に移住し、弟は借金苦で自殺した。
再起を図って上京したが、関東大震災に遭い、早々に熊本に戻る。
この頃には離婚もしている。
なんだか踏んだり蹴ったりの人生である。
42歳の時、泥酔して路面電車に立ちふさがる事件を起こした。
これはきっと自殺未遂であろう。
43歳で得度し、曹洞宗味取観音の堂守となる。
45歳、雲水姿で西日本を中心に行脚した。
ここから放浪の俳人・山頭火が生まれる。
51歳の時には再び自殺未遂を起こしたが、58歳、10月10日夜、安住の地と言っていい、愛媛県の一草庵で脳溢血で死去した。
俳壇では、山頭火が願っていた「コロリ往生」を遂げた…、と言うが、「脳溢血」が「コロリ往生」なのかどうか。
まあ、「長患いせずに済んだ」という意味では「コロリ往生」だろう。
山頭火の虫の句を挙げてみる。
酔つてこおろぎと寝ていたよ
生まれた家はあとかたもないほうたる
ほうたるほうたるなんでもないよ
いつもひとりで赤とんぼ
けふの日も事なかりけり赤とんぼ
こほろぎがわたしのたべるものをたべた
こほろぎよ、食べるものがなくなつた
蝉しぐれ死に場所をさがしてゐるのか
鳴くかよこほろぎ私も眠れない
ひとりで蚊にくはれてゐる
ほうたるこいほうたるこいふるさとにきた
松虫よ 鈴虫よ闇の 深さかな
笠にとんぼをとまらせてあるく
すッぱだかへとんぼとまろうとするか
閉めて一人の障子を虫が来てたたく
これほどまでに「虫」という小さな、ちっぽけな命に寄り添い、句を詠んだ俳人が、かつて、そして、これからもいるだろうか…、と思う。
それは「草」「花」への思いも同様である。
掲句は「行脚」の際の句であろう。
「行脚」と言えばかっこはいいが、はっきり言えば「物乞い」である。
率直に「生きる寂しさ」を感じる。
その寂しさを「とんぼ」だけが共有している。
松尾芭蕉は「おくのほそ道」に於いて「人生は旅」と言った。
近現代で唯一、「人生は旅」を実践したのは山頭火一人だ。
「旅」することの寂しさを、心底知っているのは、芭蕉と山頭火だけであろう。