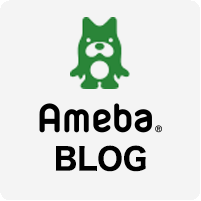『須臾の夢』加藤房子
加藤房子句集第二句集『須臾の夢』を読む 広渡敬雄
「多面性の中の揺るぎない個性」
遊ばんかかやつり草の蚊帳の中
紙ふうせん富山の薬種匂ひけり
青鬼灯むかし子供に癇の虫
蚊帳吊草の茎を両端から二つに裂いて、蚊帳を吊った様な四角形を作って遊んだ子供達。
富山の売薬のおまけの紙風船に、かすかに薬材の香が染み込んでいる、とは薬剤師である作者ならではの直感。
そう言えば、子供が発作性の痙攣を起こすと、よく虫封じに鬼灯の実をしゃぶらせたものだ。どれも郷愁を誘う句ばかりである。
紀の国の筍流し山揺るる
枡席に遍路と並ぶ渋団扇
御師の家の富士伏流の水の秋
星流れ流れ砂漠の闇無限
胡旋舞の胸乳を揺らす秋の燭
旅吟句は、その地への同化が詩を生み出す。
「筍流し」とは珍しい季語だが、筍が生える頃の雨の気配を伴う南風である。
年間降雨量が多く重畳たる紀州の山々を揺らすとは、当地でしか詠め得ないし、金毘羅歌舞伎を遍路と共に観劇するのもいかにも讃岐らしい。
富士講の案内・宿泊の御師の家。ご神体の富士山からの伏流水への視点は俳人らしく、見上げれば晴天の空に富士山頂が凛々しい。
海外詠では、ゴビ砂漠の絶え間ない流星に砂漠の闇は更に深まり、その夜の燭の中、胡族のダイナミックな踊りが眩しい。
海底に珊瑚の嬥歌月今宵
寒満月張子の兎跳ねてみよ
月光に抱かれ孕む今年竹
想像力豊かな句、戯けた句も作者の多面性の一つだが、かぐや姫伝説を彷彿させる句は、月を通じて作者のロマン性も垣間見られる。
人柱たてし長堤早稲匂ふ
読み初めは秩父一揆の起請文
青山河昼月あはき義民の碑
亡びの者への暖かな視線と慈しみが随所に詠われる。
人柱を立てた堤は洪水を防ぎ、豊かな実りで集落に恵みを齎す。
逆徒とされた秩父一揆、椋神社への誓紙を読初とし当時の秩父の民の困窮ぶりに義憤を感じる。
お上に禁制の徒党を組んだ為、指導者を祀ることが許されぬ中、密かに祀った供養碑に中七の措辞が冴える。
桐一葉母の命の澄みてきし
はまつ子の父の忌や夜の遠霧笛
臨終の母への絶唱と遠霧笛を通じて浜つ子の父への追憶が募る。
秋を痩せ夫に左右の長寿眉
今生の息一線を曳き凍つる
霜の草殯四日を声もなく
白骨の余熱は未練冬の薔薇
誰も居ぬ鍵開け寒の灯をひとつ
渾身の介護にも拘わらず、最愛の夫君が長逝しその慟哭の句は、読者に切々と迫り、誰も居ぬ冷え切った自宅は悲しみの極致である。
あさつての夢は天界虹渡る
虹渡る途中がよろし幕切れは
「虹」を通じて天上の世界への憧れを詠う。
そこはかとなく艶があるままの幕切れへの望みは、作者の矜持を見る思いもする。
新涼や掌を置けば石ものを言ふ
日照雨過ぐ苔寂光土茅舎の忌
黄身を抱く涙こんもり寒卵
暑さがやや収まり炎天で焼け付いていた石も新涼の有難さに浸り、作者に語りかける。
川端茅舎の〈ぜんまいののの字ばかりの寂光土)に対し、日照雨後の青々しい苔寂光土、著者らしい美意識である。
滋養豊かな寒卵は、割って皿に移すと、黄身の周りに卵白が盛り上がるが、その色が涙色とは生命そのものも意識させる佳句である。
身ほとりのもの捨て冬の星残る
散骨の森の転生の吾が茂る
自身の命を見定め、生きて来た証を捨て去る断捨離の句は切ないが、その転生には、青々とした森の一員としての茂りを意識する。
夏の霧寡婦も湿生花のひとつ
楽しとは生涯未完亀鳴けり
残花余花鬱のとけゆく水の音
蛤になる後ろ指さされても
一病は余生の福音大旦
せつせつと胃の腑を覗く二月尽
梅杏種までも食べ命惜し
半夏生すでに白旗身の内に
読初の語林に拾ふ志
晦日蕎麦過去も未来も須臾の夢
夫君を亡くしたのちの寡婦の生き様が真摯に詠まれ、気持ちの高揚沈鬱も日常の一面だろう。
一病も福音と前向きに捕らえ、癌発病で五年単位の区切りをつけて暮らし始めたものの、体調を崩しあと三年の命としての思いが処々に滲む。だが、まだまだ命惜しとも思い直し、読初の語林に「志」を拾う等衰えぬ気迫には頭が下がる。
句集名の句〈須臾の夢〉は、作者の究極の人生観であり、宇宙規模で見ればほんの一瞬の自分の人生を、思う存分になし遂げた充実感であろう。