雨粒に広き花びら花菖蒲 松本 美佐子『三楽章』
「朴の花」第113号~「注目の句集より」 抽出・長島衣伊子
雨粒に広き花びら花菖蒲 松本 美佐子『三楽章』
「朴の花」第113号~「注目の句集より」 抽出・長島衣伊子
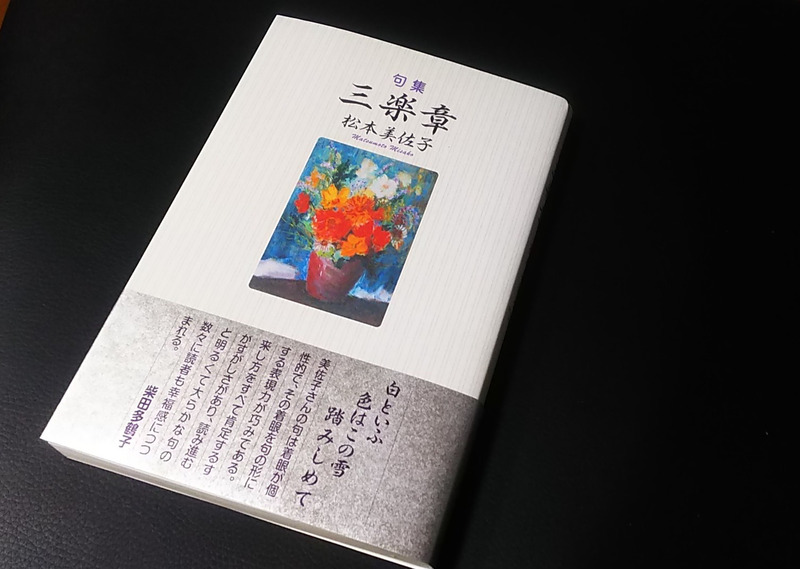
『三楽章』(俳句アトラス)は、松本美佐子の第一句集。
水に透く石寒中の五十鈴川
あともどりしたくて甲斐の桃の花
ぞの土地の決定的な〈らしさ〉の、印象的な作品化だ。
花冷の鍛冶屋に青き火の熾る
枯葉打つ雨粒ひとつづつ聞こゆ
家々の垣に赤き実クリスマス
「火」「雨粒」「実」。
現実をはみだす妖しいイメージへと昇華される。
「花冷」「枯葉」「クリスマス」との重奏が、さらに鮮やか。
沢瀉の小花を残し水昏るる
新豆腐丹波の水に切り放ち
さまざまな鯉の彩なす水の秋
三様の静謐な「水」を背景に、「残し」「切り放ち」「彩なす」の精妙な動きが、溌剌とした生命感を立ち現わす。
麻酔覚めやや傾きて眠る山
天地と人情との幽遠な交感が、言葉の個性的な組み合せによって顕現している。
1944年山口県生まれ。大阪府豊中市在住。「鳰の子」同人。
―京都新聞2021年8月17日 「詩歌の本棚」 執筆・彌榮 浩樹―
谷原恵理子句集「冬の舟」
青森県に生まれ、現在芦屋市に住む著者は、2009年俳句に出会い、山田弘子に師事。
現在は姫路の超結社「亜流里」に所属。
最初、俳句の基本は「円虹」の故山田弘子に学んだ。
「俳句を始めた頃は俳句を詠むということが特別な感じがしてずいぶん構えていました」という。
今では「起きてごはんを作り、掃除をして散歩して、俳句を作り、夜には眠る」というごく自然なこととなっていると「あとがき」に。
つまり俳句を詠むのが特別に構えることではなくなっているのだ。
桃食みて季節を一つ越す力
桃の実が出回るのは、夏バテの来る頃。
桃を食べると秋までは気力が持てて夏を乗り切れるだろう、と。
桃は昔、毛桃と呼ばれたが、近年品種改良によって現在の白桃、水蜜桃のように瑞々しい果物になった。
桃には霊力があるとも古代から考えられていたようで、古事記にもその記述がある。
その霊力で夏を乗り切るのである。
「季節を一つ」に、取りあえず今の暑さを乗り切りたいという切実な気持ちにユーモアがよく出ている。
山羊白き子を生みにけり寒の朝
この句集中一番印象に残った句。
山羊の繁殖季節は、品種や飼養されている地域の緯度などにより違いがみられる。
多くは秋口に繁殖期を迎え、春に子を産むが、この山羊は寒の朝に産んだ。
生まれると同時に子ヤギは湯気に包まれていたのであろう、白に感動が表れているという印象を持った。
白というのは色でもあるが、ことごとく純粋であるという意味もあるのだろう。
白山羊の子が白いのは当たり前のことであるが、あえて重ねて形容することで読者にも強い印象をもたらす。
吉祥の帯を仕舞へば春の風邪
春の風邪をひいた。
その原因はきっと吉祥の帯を解いて仕舞ったからだわ、という機知も働く。
石段の青きしづくや蜥蜴跳ぶ
野分中芸妓は高く褄を取り
もう戻れないかもしれぬ蛍狩
舟未だ出ぬ宇治川の残暑かな
など魅力的な句が多くあり、この人の才能の豊かさと豊潤に満ちた句集。
俳句アトラス刊。
―「神戸新聞」2021年6月22日 「句集」 執筆・山田六甲ー
句集『花鳥の譜』海野 弘子
1935年静岡県生まれ。
1992年「握手」入会、磯貝碧諦館に師事。
2007年「握手」賞受賞。
2012年「握手」終刊、長嶺千晶代表「晶」入会。
2015年句集『FLOWER』刊行。
俳人協会会員、現代俳句協会会員。
「晶」代表・長嶺千晶氏の帯文〈舞踏会へ赴くような華麗な美しさに憧れた若き日々。戦争によって封印された時代の記憶は、今、命の輝きのしずけさと蘇る。海野さんが生涯を賭して追い求めた美の形がここにある〉。
元「握手」編集長朝吹英和氏の跋文、『花鳥の譜』を通読して実在と非在、現実と幻想、精神と肉体、人生の喜びと悲しみ、そして慈愛、様々な思いや感性が重層し自由自在に飛翔する多彩な詩的空間に遊ぶ楽しみを味わった。
『花鳥の譜』十句抄より
昭和史に黒く塗りたる桜かな
白梅や弓のかたちに弓袋
天窓の新緑われは深海魚
サルビアの並列をゆく葬車かな
絵に画きて患部告げらる稲つるび
萩くくる己に容赦なきよはひ
天狼星や距離無限なる父の膝
母の忌の箸の両細さくら冷
(俳句アトラス 2,091円)
―「海」11月号(2020年)「新刊句集紹介」 執筆・秋川 ハルミ―
ピラルクのよぎつたやうな花曇 川越 歌澄
(第二句集『キリンは森へ』より)
伝統的手法を打ち破った新しい描写の句集である。
全編、巨細で細緻な描写であるが対象への執心は薄い。
掲句も解釈は鑑賞者に委ね、非合理な実存の世界へと誘っているかの様だ。
勿論、筆者は作者を哲学的人物と言っているのではなく、「それなりにけふもしあはせ毒きのこ」のような現実を肯定し、夢を見る、知的で文学的な佳句もあるのである。
氏は「人」同人。
―「対岸」11月号(2020年)「平成俳句論考」 執筆・池内 雅一―
第32回 日本伝統俳句協会賞
「水の賦(ふ)」 田中 黎子(たなか・れいこ)
昭和11年10月2日生まれ(84歳)
福岡県大牟田市在住 「さわらび」「円虹」「田鶴」
第32回 日本伝統俳句協会新人賞
「小さな冒険」 椋 麻里子(むくのき・まりこ)
昭和58年12月28日生まれ(37歳)
鳥取県鳥取市在住 「ホトトギス」
『紅の挽歌』中村 猛虎 第一句集
「ロマネコンテ」「俳句新空間」同人
ガン転移悴む指のピンホール
葬りし人の布団を今日も敷く
順々に草起きて蛇運びゆく
手鏡を通り抜けたる螢の火
独り居の部屋を西日に明け渡す
ー「星雲」第55号(2020年7月1日発行)受贈句集御礼(Ⅱ) 抄出・園部 知宏ー
『花鳥の譜』海野 弘子
あとがきの言葉「人間は誰も物理的には限られた時間を生きるのであるが精神的な時間の濃密さは永遠に繋がる」、これは作者の俳句観の根底にあるのだろう。
夏草へ沈む被爆の一校舎
冬木の芽赤子に時の無尽蔵
以下の句は心象世界へと飛躍している。
強東風や海より帰らざる魂
残照の空に残像原爆忌
言の葉の海へ漕ぎ出す初硯
―角川文化振興財団『俳句年鑑』2021年版~今年の句集BEST15
執筆・涼野海音―

―「毎日新聞」2020年3月6日 季語刻々 執筆・坪内稔典―
中村猛虎(なかむら・たけとら)、本名・正行(まさゆき)。
1961年生まれ。
2005年、句会「亜流里」設立。
2011年、風羅堂第12世襲名。
現在、句会「亜流里」代表、俳誌「ロマネコンテ」同人、俳誌「俳句新空間」同人、現代俳句協会会員。
早逝の妻に捧ぐ。
第一句集。
さくらさくら造影剤の全身に
余命だとおととい来やがれ新走
卵巣のありし辺りの曼珠沙華
秋の虹なんと真白き診断書
遺骨より白き骨壺冬の星
葬りし人の布団を今日も敷く
早逝の残像として熱帯魚
少年の何処を切っても草いきれ
手鏡を通り抜けたる螢の火
この空の蒼さはどうだ原爆忌
蛇衣を脱ぐ戦争へ行ってくる
秋の灯に鉛筆で書く遺言状
たましいを集めて春の深海魚
三月十一日に繋がっている黒電話
缶蹴りの鬼のままにて卒業す
水撒けば人の形の終戦日
心臓の少し壊死して葛湯吹く
ポケットに妻の骨あり春の虹
「跋」林誠司(「海光」代表)によれば、猛虎氏は大胆さと繊細さが入り交じる、詩情あり、ユーモアありの多彩な作品で、深みのある詩情を持っている。
芭蕉も「俳諧の益は俗語を正す也」(『三冊子』)と述べていて、彼の作品にはその伝統が引き継がれて、ひいては俳句の現代性を生み出している。
「あとがき」に、趣味でやっていた作詞作曲、その歌詞からイメージした作句は、句会で同僚の作句を圧倒し、とても気分がよかった、いっている。
(俳句アトラス 2400円(税込))
―「好日」2020年9月号 新著紹介 執筆・片岡伊つ美―